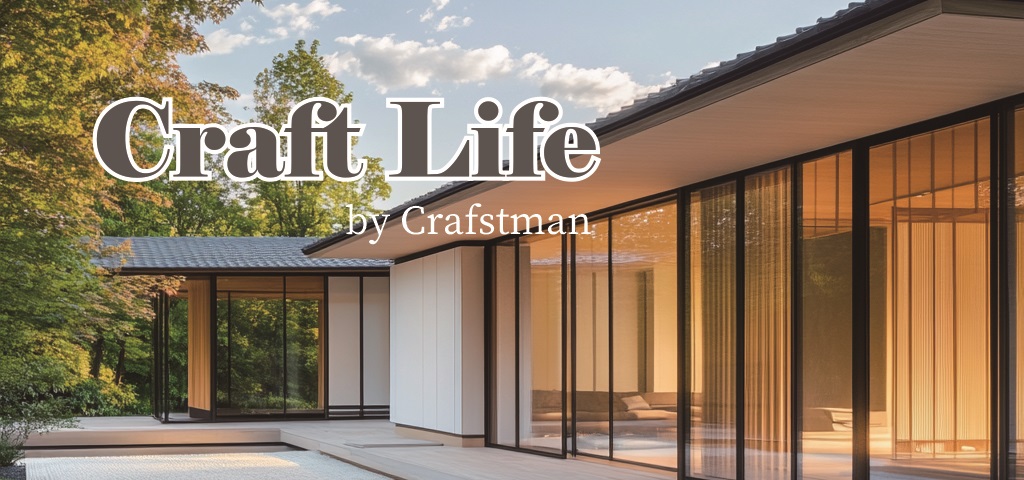はじめまして! Craftsman(クラフトマン)の三笠と申します。
「クラフトマンの家づくり」サイトにお越しいただきましてありがとうございます。
このサイトは「クラフトマン(=職人)とともに家をつくる」という趣旨ですが、この「Craftsman(クラフトマン)」には、2つの意味を込めております。
ひとつは、「手を動かしたり頭を使ったりする人が主役である」という意味で、設計・申請手続き・発注・工事・進行・監督・検証したりする人、プロの仕事をする人を「Craftsman(クラフトマン)」と呼んでいます。一方で、建設業にありがちな「一次下請け・二次下請け・三次下請け」のように、付加価値を生まない(単に間に入っている)人は含めません。「手を動かし頭を使う人」が主役です。そういうプロの仕事人が適正な報酬を得られるプロジェクトを「クラフトマンの家づくり」と定義したいと思います。
住宅の建材は種類が多く、必要な数量・コストの計算が複雑です
私は、製造業にて資材の調達・原価計算、ITシステムを担当しておりました。その傍らで、住宅用の建材、工事仕様・施工ノウハウについての研究をし、数年前に「木造住宅工事仕様書」に出合ったことを契機として、住宅工事仕様の歴史や建築基準法、建築行政についても調査をするようになりました。
資材の発注・調達の仕事を通じ、ITの力を借りてもう少し簡便にコスト計算ができないか考えるようになりました。そこで、数多くの住宅資材の中から何をどう選び、どのように発注量を決めれば良いか、そのシステム化に着手するために本サイトを開設しました。
一般の発注者(施主)には注文住宅のコスト(見積もり価格)についてヒントになる情報がほとんどありません。断片的な情報があったとしても、施主に分かりやすいように情報が整理されていないため、住宅メーカーから提示される見積書の妥当性を判断するのが難しいのが現状です。
本サイトでは、「工事の手順+建築コスト」を同時に解説し、施主が住宅工事とコストの両方について深い理解が得られるようなサイトを目指しています。どうぞご活用ください。
注文住宅の見積もりをわかりやすくするためにWebアプリを作りました
「注文住宅の見積もりをわかりやすくする」というのは、私の中では「大きなテーマ」ですが、ハウスメーカーや工務店が出す見積りは根拠が不明で「謎が多い」ものでした。
住宅メーカーや工務店からすれば、「坪単価でこれぐらいもらっておけば大丈夫」という大雑把なものであると思うのですが、発注者(施主)から見ると、非常にわかりにくく「適正であるのかどうか?」判断しにくいものになっています。施主が「何百万もボラれているのではないか」と思うのは自然なことであると思います。
「建築費アプリ・見積りシミュレーション」は、Webでもスマホでも、数字を入れれば計算結果が算出され、pdfファイルにレポート出力し、無料でメールをお送りするサービスです。無料でお送りするのは、「住宅工事の内容・建築の仕組み」を少しでも多くの方々に知っていただきたいからです。
「建築費アプリ・見積りシミュレーション」は、建築費の原価を出すことからスタートしています。
だいたいの「家の大きさ」を指定すると、必要な工事・材料の一覧とコストが出てくると便利だろうな、という思いは最初からありました。今から10年以上前の2010年ごろのことです。しかし、その時は「住宅工事は非常に複雑で、沢山の材料を使うからそれはムリ」とあきらめてしまいました。
しかし、あるとき「会計システムの原価計算」の勉強をしているときに、こうやればできるのでは?という着想が生まれました。原型はそのときにできたのですが、まだ具体性に欠けるアイデアの段階でした。その時に「住宅工事」について詳細に調べる必要があると思い、「住宅工事仕様」の研究を始めました。住宅金融支援機構の「木造住宅工事仕様書」に出合ったのはそのころです。
ここから先は非常に長い「軌跡の話」になります・・・。
お時間のある方はどうぞお読みください・・・・。
住宅工事の「仕様」はどうなっているのか?
私は、手始めに「木造住宅工事仕様書」の実物を買って研究はじめました。同時にウェブサイトで調べてみると、仕様書が「昭和26年」から存在していました。昭和26年と言えば、1951年ですので、建築基準法が制定された1950年の翌年ということになります。それまで大工さんが作っていた「家づくり」から、建築士が設計して図面を書いて、大工や職人が施工するという体制に変わった転換と言えます。
あとで分かったことですが、この動きは政策的なものでした。日本の経済発展に合わせて、ある一定レベルの品質の住宅を大量に供給して、サラリーマンが家賃程度の金額を毎月払って「35年で完済する」という仕組みに仕上げたのでした。
「20歳から働き始めて、35年経つと55歳(当時の定年の年齢)」になりますので、サザエさんの波平さんくらいの年齢になると「ご苦労さまでした」ということで「住宅ローン」の返済が終わり、「そのまま年金生活に移行する」というわけです。これは、当時は住宅メーカーにとっても、銀行にとっても良い仕組みでした。経済発展を志向する国家にとっても「まことに都合の良いシステム」だったと思います。ただ、個人的には、大正時代あるいは戦前の「日本らしい趣のある住宅」が減って、画一的なデザインのダサい家が量産されたのは、残念なことだったと思います。
1950年より以前の工事は、ほぼ「大工さん」がメインだった
話を住宅工事仕様書に戻しますが、昭和26年(1951年)の仕様書は「23ページ」しかありませんでした。その約50年後の「平成12年(2000年)」の木造住宅工事仕様書は大部の「252ページ」となっております。
最近の仕様書で「2021年版(令和3年)」を見ましたら、驚くべきことに426ページもありました。426ページもあるとは言っても「電気工事」は1ページしかなく、「ガス工事」「給排水設備工事」「衛星設備工事・換気工事」などについては、簡易な説明しかありません。住宅性能を左右するであろう「専門的な工事」については、特記仕様書によるとなっています。
1950年以前の住宅は「ほぼ大工さん」がメインの仕事でした。「住宅性能」と呼べるほどのものはなく、関東大震災(1923年)の教訓から「土台」をコンクリートで固め、最低限の「筋交い」を入れる程度の耐震性能であったと思います。家の壁もいわゆる「土壁」です。住宅工事仕様書に「断熱工事」の項目が登場したのが1979年(昭和54年)ですので、北海道などの寒冷地を除き、それまでは「断熱」という考えがなかったということになります。
昔の住宅のご記憶が残っている方もいらしゃると思いますが、「断熱」以前の壁は、篠竹を縦横に組み上げた小舞下地に「荒木田土(あらきだつち)」などの地元の土を塗って固めた「土壁」でした。今では、伝統工法の講習会にでも行かないとお目にかかれない「天然記念物ものの」工法です。
それが、1980年代・90年代に断熱工法が徐々に普及し、1981年の建築基準法改正と1995年の阪神大震災で「耐震施工」の基準が強化され、2003年の「シックハウス対策に係る法令」で質の悪い建材の使用が制限され、換気設備の実装が要求されて、ようやく「住宅性能」について語れる段階に入ったと言えます。
その後は「断熱性能」「耐震性能」「気密・換気性能」が強化されましたので、この20年間で「表に見えるところでは」住宅性能はだいぶ進歩をしたと言えます。
しかしながら、表向きと実際の施工には違うところもあることから、施主は「住宅の工事」について、しっかり目を開いて見ておく必要があると思います。
住宅の見積もり明細書は、素人が見ても解読できない
さて、住宅工事仕様書の研究がひと段落したあと、今度は住宅会社が出す「見積明細書」の研究に取り掛かりました。しかし、そこでは「仕様書」以上の苦闘が待っていました。最初に「地方の工務店が出す見積りの明細書」を取り寄せて、5社程度の「見積もり明細書」を並べて比較してみました。見比べてみて、茫然自失しました。とにかく「違う」のです。書き方も基準も。
これには「本当に参ってしまって」、途方に暮れた状態で数日間を過ごしました。日を改めて、もう一度「見積りの明細書」を読み比べましたが、解読には至りません。
まず、ひとつは「行数」が違います。ある会社の見積もりは「100行」くらいで終わっていますが、別の会社は「500行」くらいあります。「一方は細かくて、他方は大雑把である」。これは粒度の問題ですが、同じ工事の明細を比較しても表現がかなり違うのです。例えば、サッシ工事の仕様では、「アルミ樹脂サッシ」とだけ書かれていたり、あるいは「Low-Eガラス(窓の特徴)」とか「縦すべり出し(窓の形態)」「AW(アルミ窓:Aluminum Windowの略称)」「エルスター(商品名)」といった表現もあり、窓の素材・特徴・形態・略称・商品名が混在記載されているといった有様です。
「同じような2階建ての延床面積80~100平方メートル」の見積書がなぜこんなに違うのか?というのがその時の疑問で、これが一般消費者(=発注者、施主)との距離を広げているのは間違いなさそうです。
住宅の個別性(土地条件と嗜好)を反映できるWebアプリのフォーマット
苦闘を通して見えてきたのは、「住宅の仕様」の「個別性」です。
「建築費・見積もりアプリ」では、大項目で「15工事」、中項目で「150程度の材料・手間」を入れています。「木造軸組み工法 か 枠組み壁工法(ツーバイフォー)か」は、代替性のあるものなので、一方を選択すれば「そこで使用する建材・工法」に従います。
「太陽光発電:あり、なし」「ロフト:あり、なし」「浄化槽:あり、なし」というのは、オプションになりますので、接地・接続面での手間の追加を考慮してコストを算出します。
「建材の個別性」について触れると、これは本当に奥の深い世界です。
本気で選ぼうとすると「数千の選択肢」が用意された世界がいくつもある感じです。住宅会社ごとに、過去に良いと思った建材を連綿と続けて採用し、その組み合わせが個性となります。
たとえば、ある部屋の一室で「床材・壁材・幅木」を選ぶとします。「床材は木目調のいい感じのものであれば無垢でなくてOK」とは口では言ってみたとしても、実際は分厚いカタログから好みのものを選びます。
幅木(壁と床の取り合い部分に取り付ける細長い板状のもの)は「最初は何のこと?」だか分からない部材かもしれませんが、これにも数百種類あります(こだわる人はこだわります)。「壁材」となるとその選択肢は数万で、「もっとも単価の安いクロス(数千円/㎡)」の中から選ぶとしても、サンゲツの膨大なカタログなどを見ても、選ぶのに難儀すると思います。
150の「材料・手間」については、そもそも採用しなかった工程もありますが、それぞれ「10の選択肢の中から選ぶ」と仮定しても、全体では「10の150乗」通りの工事がある計算になります。膨大な組み合わせです。
同じ広さ(延べ床面積)でも見積もり金額に差が出る理由
話がだいぶ脱線してしまいましたが、本サイトでは「住宅工事のプロセス」をわかりやすく見せるための工夫をしています。
住宅を計画してから完成するまでを「15の工事+諸経費」に分けています。各工程では「設計者や営業マン、各工事の施工者」が動いた分だけのコストがかかります。
材料については「材料の単価×数量(面積に比例)」、施工については「職人の工賃×日数(工期の期間に比例)」がかかります。本アプリでは「約150の材料・工事」における建築費の概算を積算して算出しています。「太陽光発電」や「ロフト施工」「バルコニー施工」などのオプションには「推定施工面積×単価」の計算式を入れています。
住宅の見積もりにおいて、もっとも「振れ幅(価格差)」が大きいのは、「住宅メーカー(工務店)の粗利」と「材料の仕入れ単価」「施工の効率性(営業や職人の単価)」「ブランドの差」です。
「建築の原価」が下がると「見積もり金額」も下がると思われがちですが、そうではありません。住宅メーカーは「建築コストを下げる」ための努力と、「見積もり金額を上げる」ための努力を同時にしています。「値決めポリシー」の違いとも言えます。
「原材料・コスト・積算」ページでも説明していますが、材料の単価には「カタログ単価・市況単価・実際の仕入れ単価」の3つがあり、価格が高い順番に「カタログ単価 > 市況単価 > 仕入れ単価」となっています。
「建築費アプリ・見積りシミュレーション」で採用している単価は「カタログ単価(または材工共単価)」に近い価格になっていますので、それを積算した価格としては、やや高めの建築原価になっています。ただ、この見積り計算の中には「一般管理費(営業マンの人件費や本社に係るコスト」が含まれておりません。住宅メーカーから出てくる見積もり明細には、さまざまな工事のコストに上乗せする形で(この一般管理費のコストが)追加されてくると考えられます。
知識武装すれば、「満足のいく家づくり」に一歩近づきます
以上が「建築原価の研究」についての長い蘊蓄と軌跡の話です・・・。
この知識をどのように生かすかは発注者(施主)の考え方次第です。
施主がここまでの知識を持っていれば、はっきり申し上げて「一般の営業マン」よりは「住宅について知っている」ということになります。「住宅メーカー(工務店)」→「工事会社」→「職人(Craftsman)による施工」という発注の流れも理解できるかと思います。「工事の内容」が理解できていれば、住宅メーカーや工事会社をうまく使えるようになります。当然、コストコントロールもできるようになります。
住宅についての知識を上げるとキリがありませんが、現場で図面を見て「建て方での金具や筋交いの誤り」を指摘するなど、2級(または1級)建築士並のレベルまで必要かと言われると、そうではないと思います。「施主」として、明らかに知識不足の営業マンを退けることができれば、「満足の行く家づくり」に一歩近づいたと言えます。
また「思いどおりの住宅」について具体的なイメージをお持ちであれば、工事会社や建築士とタッグを組んで「住宅性能もデザインも良い、リーズナブルな住宅」を建てることもできるかと思います。
本サイトがきっかけとなって「家づくりの工程」を体系的に知り、「家づくり」そのものを楽しむ一助となれば幸いです。