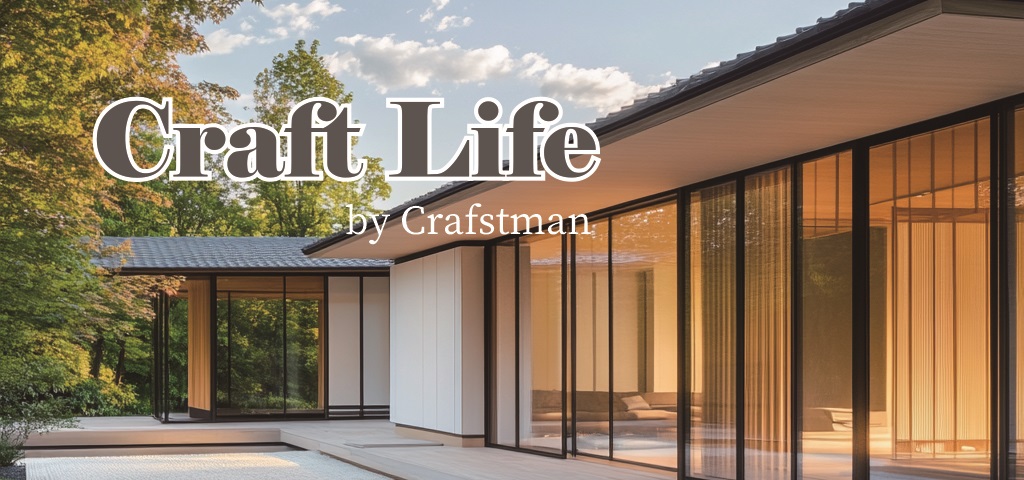はじめまして!ゆりママナースです。小学生2人の母です。今回は「5歳の子供との関わり方について」書かせて頂きました。
お子さんがいる方いない方、お仕事で子どもと関わることがある方、たくさんの方に読んでもらえると嬉しいです。
「魔の3歳」「悪魔の4歳」とよく聞きますが、では5歳はなんと呼ばれているでしょうか?
答えは「天使の5歳」と呼ばれています。この時期を待ち望んで大変な3歳4歳を乗り越えてきた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
実際はすべてのお子さまが5歳で穏やかになるわけではなく、個人差があります。天使の時間ばかりではなく、大変なことも多いんですよね…!
「◯歳だからこうなる」とは一概に言えません。「天使の5歳」は、育児の中で少し楽になったという実感を表す定番表現の一つです。言葉の発達が進み、意思疎通がしやすくなることで、保護者が育児の喜びをより感じやすくなることが背景にあると考えられます。
子どもにとっての「自己肯定感」とは何か?

子どもの頃の親や保育者との関わりは、その後の人生に大きく影響します。特にこの時期は「自己肯定感」を育む大切な時期です。
自己肯定感とは「自分は大切で価値ある存在」と感じる気持ちで、新たな挑戦や人との関わりの土台になります。
これを育てるには、大人との日々のやり取りが重要です。
「できたね」「がんばったね」など共感の言葉を通じて、子どもは自分の存在を前向きに受け止められるようになります。
聞き上手は話し上手!

周りのママ友と話していると、特に男の子は、幼稚園や保育園での出来事を細かく話す子があまり多くないようです。
うちの子もまさにそのタイプで、園での様子を聞いても「わかんない」「忘れた」と返されて、会話がそれで終わってしまうことがよくありました。
そこで私は、「今日のお弁当のおかずで一番おいしかったのは?」「どんな絵を描いたの?」など、具体的な質問をするよう意識したり、「今日は運動会の練習で疲れたね、よく頑張ったね」といった労いの言葉もかけるようにしました。
すると、「今日の卵焼き、甘くて美味しかったよ!」「園庭で育てているあさがおの観察画を描いたよ」など、少しずつ詳しく話してくれるようになりました。
それからは、自分から園での出来事を話してくれたり、「ママが今日、一番楽しかったことは何?」と聞いてくれるようにもなりました。会話が増えて、本当に嬉しかったです。
褒め方のコツ

褒めることは自己肯定感を育む大切な方法です。ただ「すごいね」だけではなく、「丁寧に最後まで頑張ったね」など、努力や工夫に注目した声かけが効果的です。
たとえば「たくさんの色を使って描いたんだね」などの具体的な言葉で伝えると、行動自体に価値を感じ、自信につながります。失敗してもいい。挑戦を認める声かけが、次への意欲につながります。
「伸びる」子どもに育つために

子どもの「伸びる力」は、人との関わりや環境の中で自然と育まれます。大人が子どもの話に耳を傾け、気持ちに寄り添い、安心できる関係性の中で自由に表現できる場をつくることが大切です。
たとえば、子どもが「これ見て!」と絵を見せてきた時、忙しくても手を止めて目を合わせ、「わぁ!たくさん色を使って、工夫して描いたんだね!」「この部分、とてもきれいに描けてるね。何を描いたの?」「どこが一番楽しかったの?教えてくれる?」などが良いですね。
このように、子どもの「努力」や「思い」に焦点を当てた言葉は、自分の作品に対して価値や喜びを感じることができます。また「教えてくれる?」これ実は子どもって大好きなんです。嬉しそうに教えてくれますよ!
また、「上手に描けたね!じゃぁ次はこの色を使ってみようか?」と、次への挑戦を促す声掛けも、子どもの成長を促します。「できる」「できない」よりも「やってみよう!」と思える心を育てることが、子どもの伸びる力を育てます。そのためには、大人の意識と声の掛け方を工夫していきたいです。
まとめ
5歳くらいの子どもとのコミュニケーションでは、「自己肯定感」を育てることが本当に大切だなと感じます。そのためには、結果だけを褒めるのではなく、子どもの「努力」や「思い」に注目してあげることがポイントです。安心できる環境で自分を表現できると、子どもは自然に「伸びる」力を育んでいきます。
そして、「子どもの話を聞く」という、ちょっとしたことだけどとても大切なことが、良いコミュニケーションのコツだと思います。子どもはキラキラした目で日常の出来事を話してくれて、少しずつ相手の話にも耳を傾けるようになります。
何気ない日常のやりとりが、子どもの「一生のたからもの」になるんですよね。だからこそ、毎日の小さな言葉や関わりを大切にしていきたいです。
(執筆者:ゆりママナース)