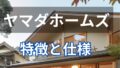小学校入学前、ワクワクとした期待感がある反面、「小学校入学の準備って、何を優先すればいいの?」「必要なものが多すぎて頭がいっぱい…」そんな悩みがつきものですよね?
初めての学校生活を迎える子どもにとって、スムーズなスタートを切るための準備はとても大切。しかし、あれもこれもと準備する中で、意外と忘れがちなアイテムやスキルがあるんです。
この記事では、つい後回しにしがちだけど「実は役に立つアイテム」や「入学前に身につけておきたいスキル」を厳選してご紹介します!この記事を読むことで、入学当日を自信を持って迎えられるようにお手伝いできれば幸いです。
【必需品編】先輩ママが選ぶ「これがあって助かった!」 忘れがちな必須グッズ

子どもの学校生活を快適にするために必要なアイテムはたくさんありますが、中にはつい後回しにしてしまい、そのまま忘れてしまうものもあります。
ここでは、先輩ママたちが「これは準備しておいて良かった!」と感じたアイテムをまとめました。余裕のあるときにチェックして、安心して新学期を迎えてくださいね!
移動ポケット(ハンカチ・ティッシュの持ち運びに便利!)
◆移動ポケット ショルダー ティッシュ
小学生になると、毎日ハンカチとティッシュを持ってくるように言われます。でも、ポケットがないデザインの服を着ることも多く、そういう時は忘れがちになりますよね。
そんなときでも移動ポケットがあれば、洋服を選ばずにハンカチ・ティッシュを持ち運べます。お気に入りのデザインを選んで、子どもがハンカチ・ティッシュを楽しく持ち運べるようにしてあげましょう。
GPS端末(子どもの安全を見守る最新アイテム)
登下校時の安全対策として、GPS端末の需要は高まっています!子どもがどこにいるかをスマホなどで確認できるため、共働き家庭や初めての一人登校でも安心です。事前に使い方を確認しておくと、スムーズに利用できますよ。
◆BoTトーク こどもGPS 親子でトークを送り合える
こちらはトークが送りあえるタイプのGPS端末です。学校帰りに迎えに行く場合など、連絡を取り合う必要があるときなどは、一方向ではなく、双方にトークを送りあえて便利です。
GPS BOTトークを使っておつかいを頼んでみた【正直レビュー】
雨具(置き傘やレインコートで急な雨も安心)
近年は突発的な雷雨が起こることも少なくありませんよね。急な雨に備えて、学校に置いておける傘やコンパクトなレインコートがあれば非常に役に立ちます。軽くて子どもでも扱いやすいものを選ぶと荷物もかさばりません。準備を忘れがちなアイテムなので、必要なものリストに加えておくと良いかもしれません。
◆レインコート キッズ ランドセル対応
こちらはランドセルを背負ったまま着られるレインコートです。ランドセルも濡れずに済みますし、傘をを持つ必要もないので便利ですね!
お弁当箱(遠足や行事で意外と早めに必要!)
「お弁当箱はまだ先でいいかな?」とか、「給食だからお弁当箱は必要ないよね?」なんて思いがちですが、遠足や校外学習などで、意外にお弁当箱には早めに出番が訪れます。
小学生にもなると食べる量も増えて、これまで使っていたお弁当箱では小さい!という子もいます。食べる量を把握したならば、子どもが自分で開閉しやすく、洗いやすいものを選んであげるとよいですね。デザインも子どもと一緒に選べば、行事の日がもっと楽しみになります。
◆弁当箱 女子 大人 子供 二段
ちなみに、小学生のお弁当箱の容量は、低学年で450~600ml、高学年で600~850mlが目安となっています。ただし、年齢や体格、運動量などによって個人差が大きいので、お子さんに合わせて選んであげてくださいね。
鉛筆削り機(学習の必需品だけど忘れがち!)
鉛筆を使って学習をする小学生にとって、鉛筆削り機は毎日の学習に欠かせないアイテムです。鉛筆削り機には手動と電動がありますが、子どもが安全に使えるものを選んであげると、学習もスムーズになります。
意外と出番の多い鉛筆削り機ですが、これまで使ってなかった家庭だと、購入することを忘れがちです。入学前に用意しておいて、鉛筆を削る練習、鉛筆削り機を使う練習をしておくと良いですね。
◆鉛筆削り 電動 小学生 鉛筆
こちらの鉛筆削り機は、充電式なのでどこでも素早く鉛筆を削れます。また、芯の太さも調節できるので、削り過ぎや削り方に不足があるなどの心配がありません。
服に穴が開かない名札クリップ(朝のバタバタを解消)
小学校では名札をピンで服に留める学校も多いと思います。服に穴を開けたくないときや、安全ピンを使いこなせなくて不安な場合に役に立つのが、服に穴があかない「名札クリップ」です。
パチンと留めるだけの名札クリップなら、子どもでも簡単に扱えますね。無くしても大丈夫なように、予備を持っておくと良いかもしれません。
◆服に穴が開かない名札留め キッズクリップ ソニック
【ママ用】携帯スリッパ&サブバッグ(フォーマル対応で好印象!)
入学式や参観日では保護者用のスリッパが必須です。しかし、子どもの入学準備に追われて、ママ自身の準備を忘れた!という話もちらほら聞かれます。また、慌てて準備しようと思っても、お気に入りのものがみつからなかったり。
また、入学式や卒業式といったフォーマルな場所に持って行くサブバックもあると便利です。せっかくフォーマルな装いをしていても、カジュアルなバッグを持っていると、残念な感じになってしまいますよね。
◆携帯スリッパ レディース
こちらの携帯用スリッパはレザー調の見た目で、オケージョンでの利用にも最適です。専用の収納ケースもあるので、持ち運びも便利です。
◆サブバッグ お受験(結婚式・冠婚葬祭)
こちらは学校行事から冠婚葬祭まで使える、マットタイプのサブバックです。容量も大きいので、一つ持っていると何かと重宝しますね。
【スキル・マナー編】小学校生活をスムーズに始めるために身につけたいこと

必要なアイテムを揃えるだけでは不十分に感じることもあるかもしれません。小学校では、学校生活で困らないための最低限のスキルやマナーも大切したいですね。入学前に少しずつ練習しておくことで、子どもが自信を持って新生活をスタートできます。
ここでは「忘れがちだけど、入学までに身につけておきたい子どもたちのスキルやマナー」についてご紹介します。
ランドセルの荷物整理術
教科書や持ち物を自分で準備して整理・整頓するスキル、小学校に入ると大事になってきますよね!学校生活が始まると、毎日異なる教科書や学用品を自分で準備する必要があります。
習い事や幼稚園の準備を自分でやってみることで、「今日は何を持っていくのかな?」と自分で考える力や責任感が育ちます。親子で一緒に確認する時間を設けるのも、最初のうちは効果的ですよ。少しずつ身につけて行く練習をしましょう。
靴の脱ぎ履き
学校では靴を脱ぐシーンが多いため、スムーズな脱ぎ履きの練習が必要になってきます。特に、下駄箱で素早く靴を出し入れできるようにしておくと、朝の登校時や授業間の移動もスムーズになりますよ。
また、靴の向きをそろえて置く習慣をつけることで、整理整頓の意識も育ちます。家庭でも日常的に脱ぎ履き、そろえて片付ける、という練習を取り入れて、自然と身につくようにサポートしてあげましょう。
トイレの使い方
学校ならではのトイレマナーやルールを確認しておけば、子どもも戸惑わずに学校生活を送れます。特に、古い学校では和式トイレが残っている場合もあります。和式トイレを使ったことがない子どもも多いので、事前に使い方を練習しておくと安心です。和式トイレでの正しい姿勢や流し方を教えることで、学校でも困らずに過ごせますね。
時間を意識した行動
授業開始時間や移動時間を意識して行動する力は備わっていますか?
時間を意識した行動は学校生活において基本となるスキルとなっているため、遅刻や忘れ物を防ぐためにも練習しておきたいですよね。時計を読む練習を日常的に取り入れ、朝の支度や遊びの時間など、日々の生活の中で「何時までに何をする」といった時間を意識した声かけをしてみると良いかもしれません。
入学準備のスケジュールをチェック!
少しの工夫と段取りで、入学準備はもっとラクになります!笑顔で入学式を迎えるために、計画的に準備を進めていきましょう!下記は大まかな準備期間についてまとめたものです。ぜひ参考になさってくださいね!
【大まかな準備期間】
| 準備日程 | 準備の内容 |
| 1年〜 6か月前 | ランドセルや学用品の検討・購入。人気モデルは早めにチェック! |
| 3か月前 | 文房具や必要なアイテムを確認し、購入を開始。子どもと一緒に選ぶと気分もUP! |
| 1か月前 | スキルやマナーの練習、持ち物の名前付けを行う。毎日のルーティンを練習しよう! |
| 1週間前 | 必要なものの最終確認と、学校までの通学練習を行う。通学路の安全確認も忘れずに! |
【まとめ】忘れがちだからこそ、少しずつ準備して安心のスタートを!
入学の準備は着々とお進みでしょうか?
どれだけ準備していたつもりでも、「忘れてしまった」、「あの時用意していれば」と後悔することはあるかもしれません。
この記事では、学校からの持ち物リストだけではわからない、先輩ママたちが「あってよかった!」と実感した、忘れがちな便利アイテムや、知っておくと安心な豆知識をご紹介してきました。
この記事を参考に、必要なモノとスキルをバランスよく整えて、入学式当日を笑顔で迎えていただけると幸いです。
(執筆者:yuffy)
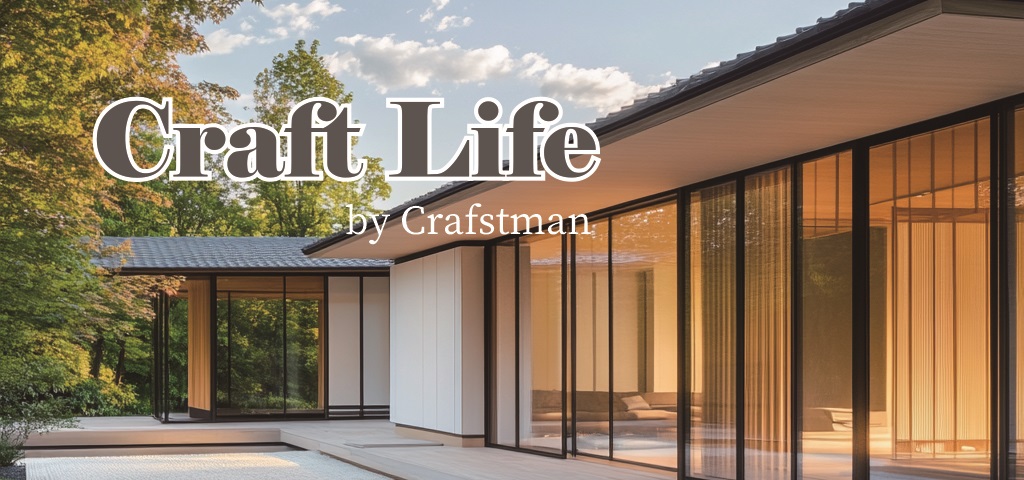

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4582a628.1f902f22.4582a629.41dabc1a/?me_id=1193359&item_id=10063899&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fangers%2Fcabinet%2Fitem_main0084%2F154029.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4582b144.b3f782a0.4582b145.acd43a1b/?me_id=1430677&item_id=10000000&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbot-shop%2Fcabinet%2Fbottalk%2Fimgrc0125516933.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4582bc72.5ed2d64b.4582bc73.c66e0a73/?me_id=1245754&item_id=10006941&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbackyard%2Fcabinet%2Fmain07%2Fr05002116.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4582c192.04573c3c.4582c193.ebb1ecb9/?me_id=1206803&item_id=10070593&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcasmin%2Fcabinet%2Fcross25%2Fs_1455_pflw4ag_01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4582c7fe.7f77a57f.4582c7ff.da91a3da/?me_id=1303915&item_id=10002041&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbestanswer%2Fcabinet%2Flife%2Flife-13%2Flife-136-w3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4582ccbc.01176478.4582ccbd.e32a58f0/?me_id=1322170&item_id=10011644&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbrucke%2Fcabinet%2F079%2F550abe424520d56.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4582d1c6.21d6d2ce.4582d1c7.aafb56ec/?me_id=1353147&item_id=10000708&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmujina%2Fcabinet%2Fitem%2Fmj-1181%2Fmj-1181_top.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4582d76d.d387fb90.4582d76e.4f60a618/?me_id=1221355&item_id=10002003&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fanworld%2Fcabinet%2F03545295%2F03625693%2Fimgrc0078324456.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)