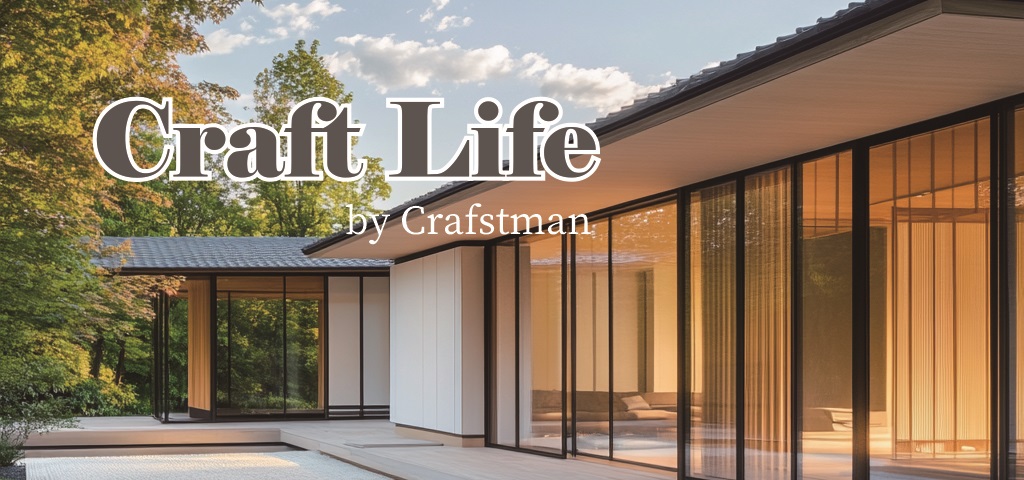(更新日:2025年3月9日)
家を買うというのは、人生の中で最も大きな決断のひとつ。特に、初めてのマイホーム購入では「どこに住むか」「どんな家に住むか」悩みが尽きません。私たちも同じように、理想の家を見つけるまでに多くの悩みや迷いがありました。
「マンションにするか、戸建てにするか」「建売りと注文住宅、どちらが良いのか」「住宅展示場をいくつも回ったけれど、決め手が見つからない」そんな時期が続きました。しかし、数々の悩みや情報収集を経て、ようやく自分たちにぴったりな家を見つけることができました。
本記事では、私たちの住宅選びの体験談をもとに、家選びで重要だったポイントや、実際にかかった時間、トラブルや解決策を詳しくご紹介します。これから家を購入する方にとって、少しでも参考になるように、私たちの「家選びの軌跡」をお伝えできればと思います。
マンション or 戸建て?
よく議論に上がるのが、「マンションか、戸建てか」という問題です。私たち夫婦は初めから戸建て派だったため、この点で意見が食い違うことはありませんでした。その理由は、以下の4つのポイントにあります。
- 子どもたちを庭で遊ばせたかったから
- 地方では車が必須なため
- 夫婦ともに高層の住環境があまり好みではないから
- プライバシーを確保しやすいから
マンションと戸建てには、それぞれ異なるメリットとデメリットがあります。ライフスタイルや優先事項によって選択が分かれる部分が多いため、自分たちのニーズに合った選択をすることが非常に重要だと感じています。
注文住宅にこだわった理由。建売でも良かった?
私たちが注文住宅を選んだ理由は、「自分たちにピッタリの家に住みたかったから」です。
実は最初は建売住宅も選択肢に入れていて、10件ほど見学に行きました。綺麗なお家に心がときめく一方で、じっくり見ると「日当たりが微妙に悪い」「良いと思った物件でも価格が高い」「間取りが自分たちに合わない」「内装の色が好みではない」「職場からの距離が遠い」など、実際に住むとなるとしっくりこない部分が多かったのです。
その結果、どうせ高いお金を払って家を買うなら、自分たちの希望に合わせて作り上げられる注文住宅にしよう!と決断しました。
住宅展示場を3か所訪問、住宅メーカーの比較検討とそのプロセス
そうと決まれば、まずは住宅展示場へ。市内には7つの展示場がありましたが、そのうち3つほどを実際に見に行きました。
最初は特に事前情報もなく、なんとなく目についた展示場に足を運びました。モデルハウスに入ると、営業マンの話がどんどん続き、最初はあっという間に1時間ほど経っていました。
矢継ぎ早に様々な情報が話され、帰る時にはパンフレットがたくさん入った重い紙袋を手にすることに。
すっかり疲れてしまった私たちは、次回から効率よく絞り込むために、インターネットの情報を参考にして住宅メーカーを絞り込むことにしました。
それでも、最終的には8種類ほどのメーカーを実際に見学しました。ここまでで半年ほどかかっていたかと思います。
住宅メーカー選びのポイント:コスパ・性能・アフターサービスを重視!
私たちが住宅メーカー選びで重視したポイントは、①コストパフォーマンス、②性能の2つです。
お金をかければかけるほど良い家が建つのは当然ですが、長期間ローンを支払い続けるのは私たちです。ですので、無駄にお金をかけ過ぎず、私たちのライフスタイルに合った家づくりができるメーカーを選びたいと考えました。
また、家の性能にもこだわりました。子どもたちと長年住むことになるため、耐震性はもちろん、断熱性や、夏と冬に快適に過ごせるかなども重要なポイントです。そのため、実際にそのハウスメーカーで家を建てた人のお宅を訪問し、見学したり、お話を伺ったりしました。
最終的に、A社とB社の2つのハウスメーカーに絞りました。両社に間取り図を作成してもらい、予算も出してもらいました。
B社は間取りの自由度が少なく、予算がオーバーしそうでした。一方、A社は間取りの自由度が高く、ローンの返済方法についても営業担当者がいくつかのシミュレーションを提案してくれたため、最終的にA社に決めました。
営業マン選びも重要! 私たちが重視したポイント
営業マンとの相性は、非常に大きなポイントです。
特に印象に残っているのは、C社の営業マンでした。
住宅展示場に行くと、住所や連絡先を聞かれるのが一般的ですが、その後、頻繁に電話や家庭訪問が続くようになりました。突然電話がかかってきて、「今週末、自社の工場見学に行きましょう!」と予定を決められたり、「近くまで来たので!」と言って急に自宅に訪問してきて、土地の話を始めたりすることがありました。
当時、私たちは二人ともフルタイムで働いており、疲れている時にそのような対応を頻繁にしなければならなくなったことが、かなりストレスになりました。何度かC社の工場見学にも行きましたが、次第にフェードアウトしていくことになりました。
一方で、最終的に決めたA社の営業マンは、押しつけがましくなく、こちらの話にじっくり耳を傾けてくれました。押しつけがましくないものの、自社の商品に対する自信が伝わる説得力のある口調で話してくれたため、徐々に心を開くことができました。
営業マンとの相性は家づくりや、家が完成した後も長い付き合いになるので、非常に重要だと実感しました。
予算、住宅ローンについて
予算は土地も含めて4000万円くらいで収まれば良いなと思っていましたが、思うような土地がなかなか見つからず、当初1000万円ほどで考えていた土地代が予算をオーバーしてしまいました。それでも、南向きで小学校にも近いという好条件が揃っていたため、将来的に娘が土地を売ることになったとしても資産になると考え、購入を決断しました。
土地が予算オーバーとなったため、家はなるべくお金をかけず、ほぼ標準仕様のものを選びました。結果的に、家はおよそ2500万円で、諸費用込みで4400万円くらいになりました。
住宅ローンを選ぶ際も、営業マンが2社に絞ってくれたおかげで、最終的には地元の銀行で40年ローンを組みました。住宅ローン減税や繰り上げ返済を上手に利用し、着実に返済を進めていきたいと思っています。
理想の広さと間取り:家族にぴったりの空間作り
私たちは夫婦ともに田舎で育ち、実家は40坪以上の広さがありました。
しかし、家を建てる場所が地方都市だったため、40坪以上の家を建てるには土地の広さや予算的に無理があり、早々にその夢を諦めました。理想としては38坪くらいあれば、かなり広々とした家になるだろうなと今でも思っています。
最終的に、総2階で34坪の家を建てることに決めました。
34坪で、総2階なので広さには限りがありますが、家族が快適に暮らせる間取りを意識しました。具体的には、玄関・キッチン・リビングには収納スペースを多めに取り、子どもが小さいうちはリビングに併設した多用途の和室を作りました。
また、脱衣所と洗面所を分け、洗面所を玄関近くに配置することで、家事動線や家族の暮らしやすさにも配慮しました。さらに、夫のトイレが非常に長いため、1階と2階にそれぞれトイレを1つずつ設けました。
目新しさはないかもしれませんが、実際に暮らしてみて、非常に使い勝手の良い間取りになったと思っています。
無垢材や壁紙へのこだわり
私たちが選んだ住宅メーカーでは、1階の床板が無垢材の標準仕様となっていたため、迷わず無垢材を選びました。無垢材は傷がつきやすいなどのデメリットもありますが、その温かみのある風合いと、裸足で歩いたときのさらさらとした質感が最高です。
リビングの広さは16畳と、決して広いとは言えない畳数になってしまいました。収納を多く取り、和室も併設したため、どうしてもリビングの広さには限りがありました。そこで、床板や壁紙の色は広く見えるように白っぽい色を選び、空間に明るさと開放感を持たせることを意識しました。建具もホワイトを基調にし、キッチンやリビングのドアにはアクセントとしてウッド調の色を取り入れました。
逆に2階は、そこまで広く見せる必要はないと感じたのと、1階と変化をつけたかったため、1階よりもワントーン暗めの色の床材や建具、壁紙を選び、落ち着いた雰囲気に仕上げることにこだわりました。
打ち合わせの回数と期間:どのくらいの時間をかけて決めたか
住宅メーカーを決定してからは、2週間に1回ほど住宅展示場で打ち合わせを行いました。間取りの決定、住宅ローン会社の決定、洗面所や風呂、キッチンのメーカー選び、インテリアコーディネーターと床や壁紙、建具の種類や色の決定、オプションの選定など、やることは本当に山のようにありました。ドアノブの色やスイッチの種類、コンセントの位置までも指定しなければならないと知り、「こんなにやることがあるのか…」と思わずにはいられませんでした。
当時、1歳の娘を連れて毎回40分ほどかかる住宅展示場に通っていたので、細かい部分については「それでいいです」となんとなく決めてしまったこともあります。後から振り返ると、もう少しじっくり考えるべきだった点がたくさんあったと後悔しています。家づくりには、想像以上に体力と根気が必要だと痛感しました。
これらの打ち合わせは約4か月ほど続いたと記憶しています。それでも営業マンからは、「かなり早い方です」と言われました。長い人だと1年以上かかる場合もあるそうですよ。
マイホーム購入で学んだこと:失敗しないために実践すべきこととは
家を購入するという決断は、人生の中でも大きな選択のひとつです。
私たちも数多くの悩みや迷いを抱えながら、最終的に自分たちにぴったりな家を見つけることができました。しかし、どんなに計画を立て、情報を集めても、家づくりには予期しない出来事や思わぬ失敗もつきものです。だからこそ、しっかりとした準備と、柔軟に対応できる心構えが大切だと実感しています。
1. 予算をしっかり守ることの重要性
予算オーバーは家づくりで最も避けたいポイントの一つです。私たちも土地が予算を超えてしまいましたが、それを後悔しないために、家の仕様やローンの選択肢に工夫を凝らしました。計画段階でしっかりとした予算を設定し、少しでも予算をオーバーしないように調整することが、家づくりをスムーズに進めるためのカギとなります。
2. 家族のライフスタイルを最優先に考える
理想の家は「外見」や「流行」で決めるのではなく、家族全員がどれだけ快適に過ごせるかを第一に考えることが大切です。私たちも家づくりの際、間取りや収納、動線などにこだわりました。生活しやすい家づくりが、長い目で見て満足度の高い結果を生むと実感しています。
3. 営業マンとのコミュニケーションを大切にする
営業マンとの相性は、家づくりを進める上で非常に大きな要素です。自分たちの意向を理解し、適切なアドバイスをくれる営業マンとの出会いが、家づくりを成功に導きます。私たちも営業マン選びに時間をかけ、お互いに信頼できる関係を築くことができました。
4. しっかりとした情報収集を行う
最初の頃、展示場での見学を繰り返し、ネットで情報を集めることを大切にしました。情報を比較することで、より良い選択ができたと感じています。特に、住宅展示場だけでなく、実際にその住宅メーカーで家を建てた人の話を聞くことが、非常に役立ちました。
5. 柔軟に対応することも大切
家づくりには予想外の出来事や変更がつきものです。計画通りにいかないこともあるかもしれませんが、その都度柔軟に対応し、最終的には自分たちが納得できる形で進めることが大切です。
家づくりを通して、多くの学びと共に一歩一歩理想の家に近づいていくことができました。これから家を購入される方々も、ぜひ焦らず自分たちにぴったりな家を見つけて、素敵なマイホームを手に入れてください。
(執筆者:AKKA)