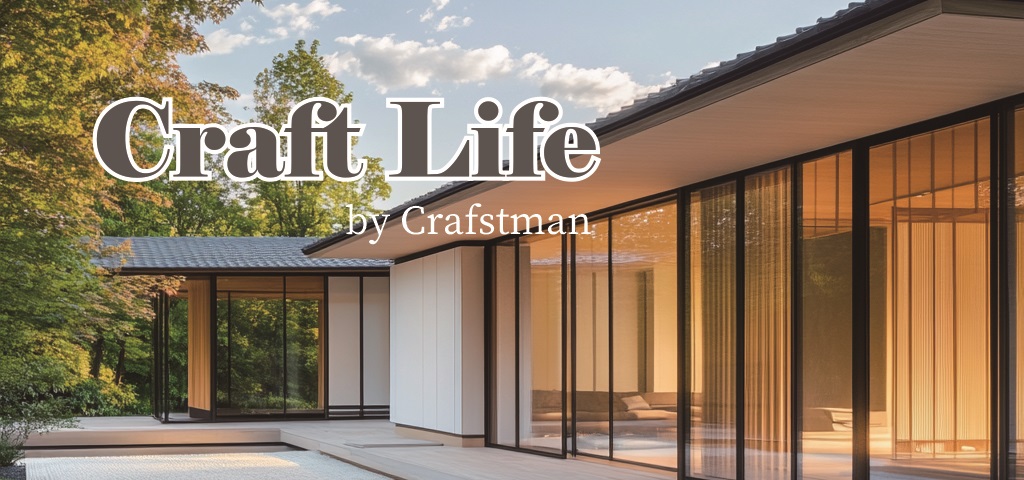近年、教員不足が深刻な社会問題となり、教員採用試験の倍率は過去最低を更新する一方で、精神疾患による休職者や欠員が過去最多を記録しています。
このままでは、未来を担う子どもたちに十分な教育を行うことが難しくなるでしょう。
今回は、10年以上小学校教諭を務めた筆者が、現場での経験をもとに教員職を若者にとって魅力的なものにするための提案を行います。
文部科学省の対策は的外れ
教員不足への対策として、文部科学省は以下のような施策を行っています。
- 教員の正規採用者数の増加
- 小学校における35人学級の整備と高学年の教科担任制の推進
- 部活動指導の負担軽減
- ICTの利活用による学校の働き方改革
- 教員採用試験の年齢制限緩和・撤廃
- 教員採用試験の実施時期の1か月前倒し(2024年から)
- 教員免許更新制度の廃止
- 大学等との連携強化(インターンシップ、教師養成塾、大学推薦特別選考)
- 4年制大学での小学校教員「二種免許」教育課程の新設(2025年から)
これらの施策のうちいくつかは、現場から見ると「的外れ」であると言わざるを得ません。
過重な業務や長時間残業が叫ばれているにもかかわらず、そこに手を付けずに採用試験の日程を前倒しにしたり、年齢制限をなくしたり、大学で免許を取りやすくしたりしたところで、志望者が増えるとは到底思えないからです。
実際に2024年は試験の日程を前倒しにした自治体がいくつかありましたが、試験の早期化と受験者数の増加に明確な相関関係は見られませんでした。
元教員が考える5つの提案
教育現場の実情を見てきた筆者が、教員を魅力的な仕事にするための5つ対策を考えました。
業務の削減、明確化
最も重要なのは、業務の削減です。現状、残業代が支払われないにもかかわらず、勤務時間内で業務を終わらせることは非常に難しく、長時間の残業が常態化しています。
勤務時間内に終わらない業務は、削減対象として検討すべきです。「子どもたちのため」という名目で、現場では業務がどんどん増えていっていますが、「あったら嬉しいけど、なくても困らない」ようなものは削減すべきです。
例えば、行事についても、運動会では短距離走やダンスのみを行い、昼食を省略するなどの簡素化が可能です。また、学習発表会では、劇を省き、音楽などの授業で学んだ内容に絞ることも現場レベルで実現できます。
文部科学省の「総合的な学習の時間」についても、各学校に任されているカリキュラムが現場の負担になっています。これを思い切って廃止することで、国語や算数などの教科に充てる時間を増やすことができます。
教員自身が健康で、精神的な余裕を持てなければ、質の高い学級経営は難しいです。現場レベルでも、文科省レベルでも、削減できる業務は思い切って見直し、減らしていくべきだと考えます。
初任者へのサポート
現状、教員として採用されると、4月1日に各学校に赴任し、数日後には学級担任として最大35人の児童を指導しなければなりません。このシステムは、大学を卒業したばかりの若者にとって非常に負担が大きいと考えます。
集団を効果的に動かすには技術が必要です。いくら大学で学び、数週間の実習を経て、試験に合格したとしても、初任者が完璧に学級経営を行うのは至難の業です。
さらに、35人の子どもたちの背後には70人以上の保護者がいます。おそらく自分より年齢がかなり上の保護者と「教育のプロ」として対応していかなければならない場面も多いでしょう。昭和時代は「若い先生を育てる」という意識が強かったようですが、最近では若い担任を「ハズレ」と評価する保護者も少なくありません。保護者対応にも一定のスキルが求められます。
そこで、初任者には学級担任を任せず、1年間は専科や学級の補助としてさまざまな学級に入ることで、先輩教員の技を学び、1年後に初めて学級担任を持つという制度が有効だと考えます。
この取り組みを実現したのが山形県です。この制度は新卒教員にとって理想的なものと言え、全国に広まるべきだと強く感じます。
休憩時間の確保
労働基準法では、1日の労働時間が6時間を超える場合、少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与えることが義務付けられています。しかし、教員の実際の勤務実態を考えると、この法的要件が守られていない場合が多いのではないでしょうか。
私自身も教員時代、勤務時間中に休憩を取ることができた記憶がありません。朝から夕方まで働きづめの職業を、ワークライフバランスを重視する令和の若者が志望することは少ないのが現実だと思います。
そのため、一人一人の職員が適切に休憩を取れるような仕組みを導入し、実行していくことが求められています。職場環境を改善することで、より多くの若者が教員という職業に興味を持ち、長く続けられる環境が整うことが重要です。
一クラスの人数を25人に
コロナ禍をきっかけに、小学校の一学級の最大人数は、3年生以上で40人から段階的に35人に変更されました。しかし、それでも35人という人数は、諸外国に比べると非常に多いと言えます。
2024年のOECDの調査によると、小学校の学級の人数は、アメリカのテキサス州が最大22人、ドイツは30人、フィンランドは25人、イギリスは14人と、先進国の中でも日本の人数は群を抜いて多いことがわかります。
一学級の人数が多くなると、当然ながら目が行き届きにくくなります。丸つけや家庭訪問、成績処理などの作業も、人数が増えるほど増加し、長時間残業の原因になります。
実感として、最大25人程度が、一人の教師が無理なく指導できる人数だと考えます。
教員を「守る」仕組みづくりを
教員として10年間勤務してきた中で、たくさんの素晴らしい保護者に出会い、今でも感謝しています。大多数の保護者は協力的ですが、一部には自分勝手な無理難題を要求する方もおり、そのような保護者には常に頭を悩ませてきました。その結果、毎日のようにクレームを受け続け、最終的に退職してしまった同僚も見てきました。
現状、そのような保護者に対して、担任は言われっぱなしで対処法がなく、苦しんでいるのが実情です。「カスハラ」という言葉が広まりつつありますが、学校側も明らかに不当なクレームに対しては毅然と対応すべきです。特に、人格否定や暴力などの行為に出てきた場合は、警察や専門機関に連携することが必要です。また、そのような状況が実際に起こり得ることを保護者にも周知させていくことが重要だと考えています。
まとめ
現在の教員不足の深刻な問題に対処するためには、採用数の増加や業務の効率化だけでは不十分です。
教員が長く続けられる職場環境を作るためには、業務の削減や初任者への支援、休憩時間の確保、一クラスの人数の削減といった具体的な改革が不可欠です。また、保護者からの過剰な要求に対しても学校側が毅然と対応し、教員を守る仕組みづくりを進めることが求められます。
これらの取り組みを進めることで、教員職がより魅力的で持続可能なものとなり、令和の若者の職業の選択肢になり得ると考えます。
(執筆者:AKKA)