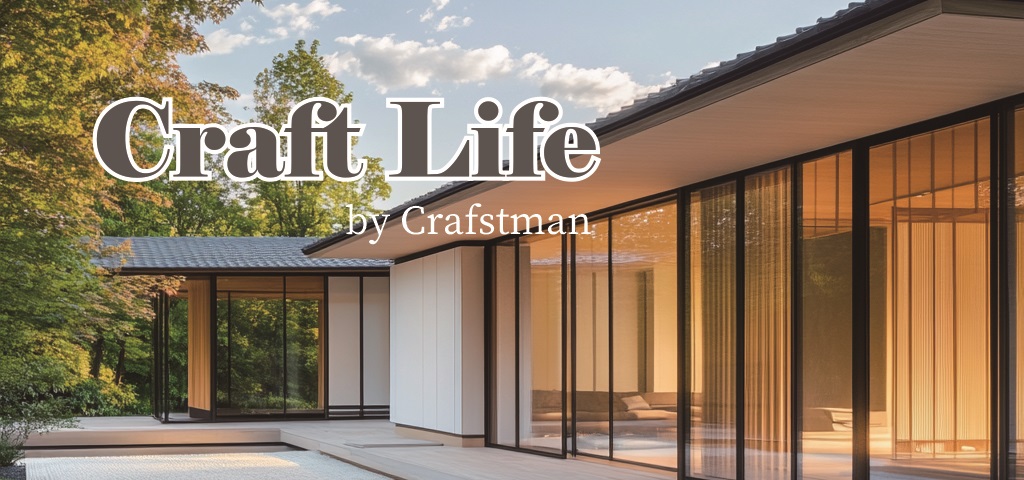(更新日:2025年2月21日)
日本の公立学校における教員不足の問題が、年々深刻化しています。
2024年5月時点で、全国の未配置教員は少なくとも4000人以上に上り、半数以上の学校で1名以上の教員が欠員状態にあるとの調査結果も発表されています。また、教員採用試験の倍率は年々低下し、2025年度には倍率が2倍を切る地域もあると予測されています。
なぜ、未来を担う子どもたちを教え育てるという尊い仕事が、若者に敬遠されるようになったのでしょうか。
小学校で10年以上の勤務経験を持ち、退職した元教員として、現場の実情から教員不足の原因に迫ります。
学校教員は本来魅力にあふれた仕事
小学校教諭として10年以上の経験を持つ筆者ですが、学校教員という仕事には本来、大きな魅力があると感じています。さまざまな可能性を秘めた子どもたちとともに学び、生活し、一人一人の力を伸ばしていく喜びは、他の仕事では味わえません。教員としての10数年の経験には困難も多くありましたが、それ以上に素晴らしい出会いや喜びがありました。
また、学校教員は同年代の他の職業と比べると、給与が平均以上であることも魅力の一つです。福利厚生も充実しており、育児や介護のための休暇も豊富です。さらに、社会的な信用が高いため、ローンを組む際も有利に働きます。また、公務員としての安定性があることから、特に50代以上の方々には、安心感を持っている方も多いのではないでしょうか。
採用試験の倍率は過去最低
上記のようなメリットがあるにもかかわらず、教員採用試験の倍率は年々低下の一途をたどっています。平成12年度の13.3倍をピークに徐々に低下し続け、令和5年度の全国の自治体の平均倍率は3.4倍となりました。
令和6年度の東京都を例に挙げると、最終倍率は1.6倍でした。校種別に見ると、小学校1.1倍、中高1.9倍、特別支援学校0.9倍、養護教諭6.6倍となっており、1倍を切る校種も出てきてしまっています。
この教員不足は結果的に学校に通う子どもたちにしわ寄せがいくことになり、由々しき事態と言えるでしょう。
教員=ブラック? 元教員が考える倍率低下の理由
ここまで教員が若者に不人気な職業になってしまったことにはたくさんの理由があると考えます。現場で10年以上働いてきた元教員が考えるその理由を述べていきます。
過労死ラインの残業時間で残業代はナシ
全日本教職員組合が2023年に発表した調査結果によると、公立学校教員の残業時間の平均は以下の通りです。
- 小学校教諭:月平均93時間48分
- 中学校教諭:月平均113時間44分
- 高校教諭:月平均95時間32分
これらの時間は、国が定める過労死ライン(80時間)を大きく超えています。
長時間労働の背景には、授業時間の増加、報告書作成などの事務作業、部活動指導などが挙げられます。ですが、1971年に制定された法律「給特法」により、教育職員には、給料月額の4%に相当する額を教職調整額として支給するかわりに、時間外勤務手当・休日勤務手当を支給しないことが明記されています。基本給が300,000円の場合、教職調整額は12,000円となり、とても十分な額とはいえないでしょう。
特に部活動については、顧問を担当しても平日の部活動に対する手当はなく、休日は手当が支給されるものの、4時間程度で日給3600円という状況です。自給換算すると700円程度となり、最低賃金を下回っています。また、交通費や昼食代、運動部を担当した場合の審判資格取得費用などが自己負担であることが多く、金銭的な負担も大きいです。
精神疾患による休職者が過去最多
さらに、2023年度の公立学校教職員の人事行政状況調査によると、教育職員の精神疾患による病気休職者数は過去最多の7,000人を超えました。これは全教育職員数の約0.76%に相当します。生徒や保護者との人間関係や多重な業務が原因と思われますが、これについても近年マスコミで大きく取り上げられるようになったため、若者にとってよりブラックなイメージが強まる一因となっていると思われます。
実際、現場で十数年働いていた間に、精神疾患を理由に休職や退職をする同僚を何人も見てきました。休職者が一人も出ない年度の方が珍しく、「あの人は大丈夫だろう。」と周りから信頼されているベテランや実力のある教員も、あるきっかけを境に体調を崩してしまうことがしばしばありました。私自身も「明日は我が身」と思いながら働き続けていました。
一度メンタルを崩してしまうと、回復には時間がかかります。そのため、「そこまで自分を犠牲にして働き続けなければならないのか?」という疑問は、教員時代に何度も感じていました。
多重な業務
上記のように残業代が出ないにもかかわらず、とても業務時間内に負えることのできない仕事量を抱えているのが現状でした。
1日の流れを例に出すと、
1.朝7時半~8時ころに出勤(始業時間は8時15分)
2.8時半~15時過ぎまで6時間授業(休み時間は子どもと遊ぶ、給食時間も指導のうち)
3.15時半~16時45分までの放課後は、会議・保護者への連絡・アンケートや報告書作成・お便り作成・行事の準備・研修・不登校の子どもへの連絡や家庭訪問・校務分掌とよばれるそれぞれに分担される学校業務・テストや提出物の丸つけ、評価・次の日の授業の準備・教材研究・成績処理 など
という流れでした。ちなみに、休憩時間は16時~16時45分に設定されていましたが、業務時間内に業務を終えようとすれば休憩を取る時間などありません。休憩時間に仕事をしても、業務を終えることができるはずがなく、残業か持ち帰って仕事をするかということをしていました。
独身のうちは、学級の子どものためにと思い、長時間の残業も苦に感じませんでした。しかし、結婚して自分の子どもを持つようになってからは、無理が出てきてしまい、最終的には退職を選ぶことになりました。子どもができても教員を続けていたかつての同僚は、毎晩21時に我が子を寝かしつけ、朝2時に起きて学校業務の残務をこなしていると話していました。このような生活を続ければ、いずれ心身に不調が出てしまうのは避けられないでしょう。
ワークライフバランスを考える若者
近年、女性の社会進出や少子高齢化、長時間労働による健康問題が社会的に注目されるようになり、「ワークライフバランス」を重視する考え方が広まっています。
コロナ禍をきっかけにリモートワークやフレックスタイム制が普及し、男性の育児休暇取得も注目を集める中、これから社会に出る若者にとって「ワークライフバランス」は非常に重要なテーマとなっています。
彼らは、仕事と私生活の境界線をはっきりと引く傾向にあります。「働くために生きる」のではなく、「生きるために働く」という考え方を持っているのです。昇進や高給よりも、生活の質や幸福度を重視する若者にとって、ブラック労働が初めから予想される教員という職業は、いくらやりがいがあっても選びづらくなっているのではないでしょうか。
売り手市場の就職活動
業界や企業規模によって状況は異なり、一概には言えませんが、令和の若者の就職活動全体を見ると、売り手市場の傾向が続いています。
かつては狭き門だった教員採用試験ですが、今では倍率が低下し、一般企業での経験を積んでからでも教員になれる時代となっています。また、年度途中でも病休や産休・育休による欠員を補うための期限付き求人が多く、教員免許さえあればほとんどの自治体でいつでも働ける状態です。
一度しかない「新卒カード」を使ってまで教員になるメリットは、今の若者にはほぼないと言えるでしょう。そのため、教員を志望する若者が減少しているのは、必然的な流れと言えます。
まとめ
日本の公立学校における教員不足は、今後ますます深刻化する可能性があります。教員という職業は、教育という重要な役割を担い、社会的な信頼と安定性もある魅力的な仕事です。しかし、長時間労働や過酷な労働環境、精神的な負担が若者にとって大きな障壁となり、教員を目指す人が減少しているのが現実です。
現場での過重労働、ワークライフバランスを重視する若者の価値観、さらには売り手市場が影響し、教員採用試験の倍率が低下しています。この状況は、結果的に子どもたちに悪影響を及ぼし、将来的な教育の質にも関わる重要な問題です。今後、教員不足を解消するためには、教員の働き方改革と労働環境の改善が急務であると言えるでしょう。
(執筆者:AKKA)