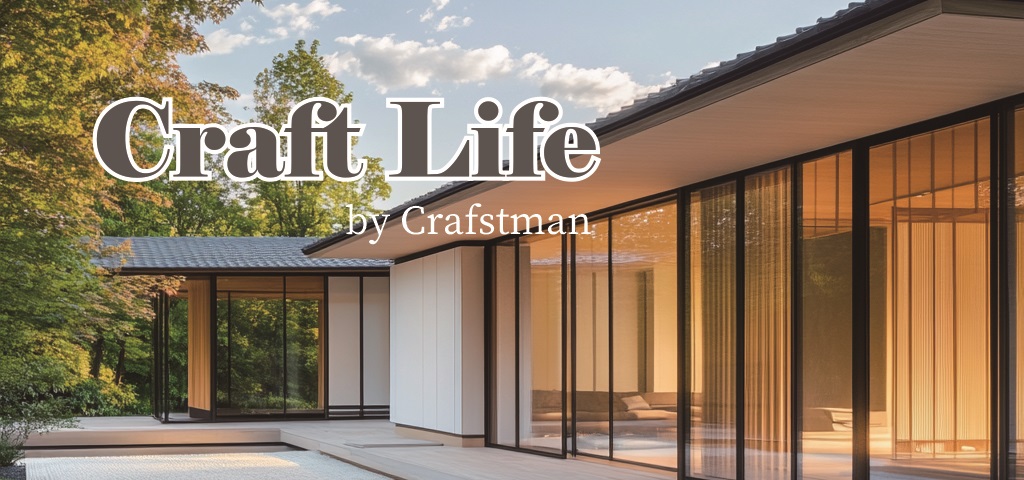(更新日:2025年3月9日)
小学校の入門期における「国語力」の向上は、学力の土台を築くうえで非常に重要です。
国語力が高まることで、算数や理科、社会など、他の教科の理解力も向上します。また、国語力は、日常生活や将来的なコミュニケーションスキルにも深く関わっています。
しかし、最近の子どもたちは、じっくり考える力が乏しく、即答を求める傾向が強いです。本記事では、10年以上小学校で担任経験のある元教諭である筆者が、教諭時代に実践していた具体的な学習方法と、家庭でできる国語力向上のアプローチを解説します。
お子さんの成長に欠かせない国語力をどう育てるか、一緒に考えていきましょう。
国語力は全ての教科の土台
近年、小学校に外国語が教科として導入され、注目を集めていますが、私は外国語の前にまず「国語力」をしっかりと身に付けるべきだと考えています。
国語力は、学びの土台となる重要な力です。私たちが学習を進める上で使用するのは日本語ですから、国語力の向上はどの教科にも深く関わるのは当然のことです。しっかりとした国語力を育むことは、他の全ての教科の成績向上にも繋がります。
例えば、ペーパーテストの場面を考えてみましょう。算数では、計算が得意な子でも、問題文の意味を正確に理解できず、問題文に出ている数字だけを拾って立式し、間違えてしまうことがよくあります。さらに、高学年になると、理科では「なぜその実験結果が出たのか」といった記述問題が増えてきます。ここでも、しっかりと根拠をもって論理的に文章を構築する力がなければ、思うように解答できません。このように、国語力はすべての教科で求められる力であり、最終的には全ての成績に直結しているのです。
国語力はコミュニケーションスキルにも直結
国語力は、子どもたちのコミュニケーションスキルにも大きく影響します。
教室には、最大で35人もの異なる個性を持つ子どもたちが集まり、集団生活を送ります。そのため、トラブルが起こることは避けられませんが、国語力のある子どもは、問題が発生した背景や、自分の感情、現在の困りごとを上手に言葉で説明することができます。また、相手の気持ちを想像し、解決策を考える力も高いです。
特に近年、子どもたちの語彙力の低下を強く感じることがありました。自分の気持ちをうまく表現できず、「きもい」「うざい」「しね」など、強い言葉を使ってトラブルがエスカレートすることが増えています。話をじっくり聞くと、「○○が嫌だったからイライラした」「相手にこうしてほしかった」「本当はこんな気持ちだった」といった気持ちが見えてきますが、そこにたどり着くまでに膨大な時間がかかることが多いのです。
もちろん、国語力の低下が直接的な原因でトラブルになるわけではありませんが、自分の思いを適切な言葉で表現できるようになることは、確実にコミュニケーション能力の向上に繋がると言えるでしょう。
最近の子ども…すぐに答えを求めたがる傾向
最近の子どもたちは、すぐに答えを求めたがる傾向が強くなっています。
例えば、調べ学習を進めても、「タブレットを使ってもいい?」と、すぐにタブレットを使って調べようとする子が多く、クラスの約3分の1から半数ほどがそのような反応を示します。しかし、タブレットで得られる情報はソースが不明確なこともあるため、図書室での調べ学習と時間を分けて行うようにしていました。
また、ペーパーテストでも、単語や選択肢を選ぶ問題は解ける子が多い一方で、記述式や深く考えることが求められる問題には空欄で答える子が増えてきました。
また、作文等で自分の意見や感想を記述する場面でも、「どっちでもよい。」「分からない。」と答える子も増加していたように感じます。
近年、急速にデジタル化が進み、いわゆる「デジタルネイティブ」と呼ばれる子どもたちは、YouTubeやSNSなどに早くから親しんでいます。これらのメディアは次々と新しい刺激的な情報を提供し、瞬時に消えていきます。このようなデジタル環境は、確かに便利な側面もありますが、一方で、深く思考することから遠ざける原因の一つにもなっていると感じています。
教諭時代にしていたこと
子どもたちの国語力を伸ばすために、教諭時代に実践していた方法をいくつかピックアップして紹介します。
読み聞かせ
特に低学年を担任していた時、授業の時間が余った際には、読み聞かせを行うようにしていました。これには主に、①語彙力や読解力を向上させること、②「話をしっかりと聞く」という経験を提供することが目的でした。
普段落ち着きのない子どもたちでも、読み聞かせの時間になると、じっくりと聞き入る姿が見られます。「聞く」ことに集中することは、すべての教科の学力向上につながります。この「聞く」という行為を通じて、子どもたちに集中力を養わせることを大切にしていました。
また、絵本を読み終わった後は、数人に感想を話してもらうようにしていました。自分の思いを「話す」経験を、楽しみながら行うことで、人前で話すことへのハードルを低くすることを意識していました。
音読
特に低学年において音読は非常に重要です。音読が宿題として出される学校も多いのではないでしょうか。
教科書の文章は、専門家が練りに練った内容です。それを声に出して読むことによって、熟語の意味や文法など、正しい日本語を無意識のうちに身につけることができます。この習慣を通して、言葉の使い方や文章のリズムを自然と体得させることが目的でした。
日記
子どもたちにはその日あった出来事を3行以上で書くという条件をつけて、定期的に日記を書かせていました。
「自分の意見を書く」という行為に対してハードルを感じる子どもが多かったため、最低条件として5W(誰が、何を、いつ、どこで、なぜ)を意識して書かせるようにしていました。これにより、文章を書く際の具体性や整理された構成を学ばせることができます。
まずは「書く」という行為に慣れ、経験を積むことで、徐々にハードルを低くしていくことが大切です。
立場を決めて意見を戦わせる
こちらは中学年以上のクラスでよく行っていた活動です。授業の初めにペアを組み、ミニゲームのような形で意見を戦わせることがありました。
例えば、「犬派か猫派か」「きのこの山派かたけのこの山派か」など、身近な題材を取り上げて、二人の間で立場を決めます。
「私はおやつに食べるならきのこの山がいいと思います。理由は~だからです」と意見を述べさせ、相手には「確かに、きのこの山は~ですね。しかし、たけのこの山は~」と反論をさせます。このように、ゲーム形式で議論を進めることで、論理的に意見を述べる力を養うことを目指していました。
家庭でできることは?
上記を踏まえると、家庭でもできることはたくさんあると思います。
読書習慣をつける
よく言われることですが、最も重要なのは読書習慣を身につけること。実際に、学級の子どもたちを見ても、読書習慣のある子どもは語彙力や知識が豊富で、国語の成績も高かったです。
未就学児や小学校低学年であれば、地域の図書館を利用してさまざまな本に触れさせることが有効です。また、読み聞かせも効果的です。図書館の利用はお金もかからず、親にとっても便利な方法です。本を選ぶのは親でも良いですが、子ども自身が興味のある本を選ぶことも大切です。
「うちの子は読書をしない」とおっしゃる保護者の方もいらっしゃいますが、まずは保護者自身が読書する姿を子どもに見せていますか?もちろん、子どもには個性がありますが、「本を読みなさい」と言いながら、親がテレビやスマホばかりだと、子どもは読書に向かうことが難しくなります。休みの日などは、たまにテレビを消して「読書タイム」を設けると良いかもしれません。
家族の会話を大切にする
現代の親は共働きで忙しいため、家族そろって食事がとれなかったり、家族の会話が少なかったりします。子どもが好きなこと、学校であったことを把握する余裕がないという保護者の方も多いです。
例えば、食事の時間はテレビを消して今日の出来事を話し合うなど、子どもと積極的に会話をすることで、語彙や表現力が自然と豊かになります。子どもの発言に対して、質問をしたり、意見を求めたりすることで、考えを深めることができます。その際、子どもの話をポジティブに受け止め、反応してあげることが大切です。
辞書を引く
家庭の中で、子どもから「○○って何?」「○○ってどういうこと?」とよく質問されることはありませんか?特に好奇心旺盛なお子さんには、日常的に起こることです。
そんな時、国語辞典を使って、言葉の意味を正しく教えてあげることが、語彙力を向上させる一歩になります。もちろん、スマートフォンやタブレットで調べることもできますが、これらのデジタル端末は情報が多すぎて、集中して調べるのが難しいこともあります。一方、紙の辞書に触れることで、情報を整理して受け取る力を育むことができます。
現在、小学3年生で国語辞典の使い方を学びますが、使いこなせるようになるまでには時間がかかります。辞書には、言葉の意味だけでなく、類義語や対義語、例文も載っているため、日常的に辞書を使わせていれば、自然と語彙力が高まるでしょう。
まとめ
国語力は、単なる学力の一部にとどまらず、子どもたちの未来を支える大切な力です。学ぶ力を支える基盤として、また、コミュニケーション能力を育む土台として、家庭でも学校でも国語力を高める方法は数多くあります。
子どもたちの成長には時間がかかりますが、日々の積み重ねが大きな変化を生み出します。家庭でできることから始め、小さな一歩を踏み出すことが大切です。共に学び、共に成長する中で、お子さんの国語力も確実に伸びていくことでしょう。
(執筆者:AKKA)