(更新日:2025年3月30日)
「知育にいい本ってどれ?」
「子どもの成長を助けるおすすめの絵本が知りたい!」
そんな疑問やお悩みをお持ちではありませんか?
子どもの成長をサポートするために知育本を選びたいけれど、種類が多すぎて何を選べば良いのか迷ってしまう方は少なくありません。
そこで本記事では、絵本と知育玩具本の中から特におすすめの10冊を厳選してご紹介します。
さらに、知育本を選ぶポイントや年齢別のおすすめ本の特徴、読み聞かせの効果についても紹介しています。
お子さんの成長をサポートする知育本を探している方は、ぜひ最後までご覧くださいね。
知育絵本がもたらす効果とは? 子供の成長をサポートする4つのポイント
絵本は、子供の豊かな感性と知性を育むための素晴らしいものです。読み聞かせを通して得られる効果は、単なる知識の習得にとどまりません!ここでは、知育絵本がもたらしてくれる、子どもの成長を後押しする力についてご紹介します。
知育本の読み聞かせで子どもの成長をサポート
知育本は、単なる娯楽としてではなく、子どもの成長に大きな影響を与えてくれます。ここでは読み聞かせを通じて得られる4つの効果についてご紹介します!
- 想像力が豊かになる!
絵本の世界は、子供の想像力を無限に広げてくれます。鮮やかなイラストや魅力的なストーリーに触れることで、子供たちは頭の中で自由にイメージを膨らませ、自分だけの世界を作り上げていくことができます。
- 言葉の力が伸びる!
絵本は、子供たちが言葉の世界に触れる最初の一歩です。豊かな表現やリズム感のある文章に触れることで、自然と語彙力や表現力が身についていきます。
- 感情が豊かになる!
絵本に登場する人物たちの喜びや悲しみ、怒りや楽しさといった様々な感情に触れることで、子供たちは共感する力を育んでいきます。
- 集中力がアップする!
絵本の世界に夢中になることで、子供たちの集中力が育まれます。
読み聞かせは、親子の絆を深める大切なコミュニケーションの時間でもあります。子供たちは、優しい声で絵本を読んでくれる親の愛情を感じながら、安心して絵本の世界に浸ることができます。
親子で楽しめば知育本の効果はさらにUP!
知育本の効果を引き出すには、親子で一緒に楽しむ工夫が大切です。以下に具体的な方法をご紹介します。
- 読み聞かせの時間を日常に取り入れよう
読み聞かせは、日常の中で定期的に取り入れることが大切です。寝る前のひとときや、休日のリラックスタイムなど、親子がゆっくり過ごせる時間を活用しましょう。時間を決めることで、子どもが楽しみにする習慣が作れますよ。
- 親も一緒に楽しむ姿勢を
親が楽しんで本を読んでいる姿は、子どもにとって最高の手本になります。本の内容について一緒に話したり、感想を言い合うことで、子どもの学びや興味がさらに深まっていきます。
【2025年最新】売れている!知育本おすすめ10選
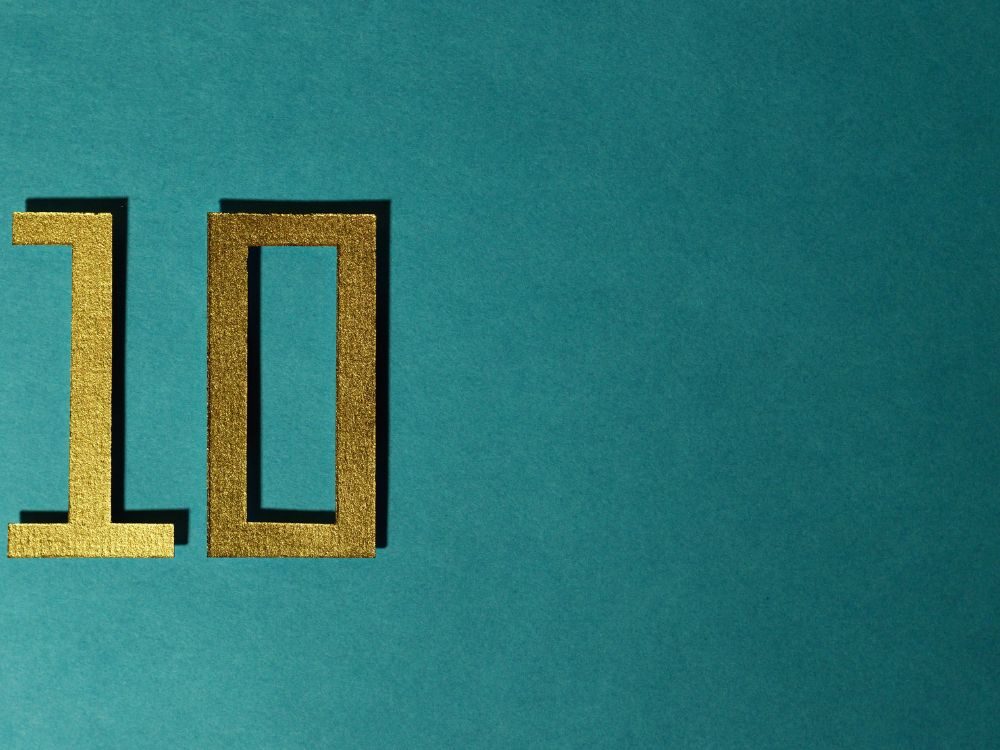
ここでは、実際に評価が高く、人気のある知育本を知育絵本と知育玩具本に分けて、それぞれ5冊ずつ、10選をご紹介します!
絵本タイプのおすすめ知育本5選!
◆しましまぐるぐる (いっしょにあそぼ)
カラフルで厚みのある表紙は、絵本としてだけでなくおもちゃとしても安心感があります。カラフルなぐるぐるやしましまには、おもわず赤ちゃんでも見入ってしまう魅力があります!まずは見て触って、次は読み聞かせて。何度でも楽しめる知育本のベストセラーです。
発売日: 2009年04月
著者/編集: かしわらあきお(絵)
出版社: 学研プラス
ページ数: 24p
◆はらぺこあおむし
20年以上前から愛されている絵本の名作。色鮮やかに描かれたアオムシ、食べ物、チョウチョだけでなく、アオムシが食べたあとにできる小さな穴の仕掛けにも子どもたちは興味心身!指を入れたり覗いたり。読み聞かせだけでなく、歌でも楽しめるのがポイントです。
発売日: 1997年04月
著者/編集: エリック・カール、森比左志
出版社: 偕成社
ページ数: 25p
◆きらきら ぴかぴか
子どもたちが思わず手を伸ばす、きらきら光るホログラムは赤ちゃんにも人気。視力が未熟だと言われている乳児期の赤ちゃんにも届く強い光やピカピカの光で、脳にも好影響を与えてくれます。本自体もしっかりした作りなのでプレゼントにも最適です。
発売日:2022年10月
著者/編集:瀧靖之(監修) あかいしゆみ(絵)
出版社:朝日新聞出版
ページ数:16p
◆「だるまさん」シリーズ 3冊ケース入り
こちらも人気の「だるまさん」シリーズ。三冊がセットになったギフトセットです。「だ、る、ま、さ、ん、が」の言葉に続くだるまさんの動きがおもしろくて可愛い!リズミカルな言葉は、次に何がくるのかな?と大人もワクワクできます。
発売日:2009年09月
著者/編集:かがくい ひろし(著・絵)
出版社:ブロンズ新社
ページ数:20p
◆ねないこ だれだ
40年近くベストセラーであるこの絵本は、子どもたちが怖がる「おばけ」のお話。怖いもの見たさで何度も読み返す子、黄色い目のおばけに会いたくて繰り返し読んでしまう、不思議な魅力を放ち続けているこの絵本を使って早寝の習慣をつけるのも良いかも知れませんね。
発売日:1986年09月
著者/編集:せな けいこ(著・絵)
出版社:福音館書店
ページ数:24p
はらぺこあおむしのうた 【The Very Hungry Caterpillar Song】
知育玩具本タイプのおすすめ5選!
◆あかまる ぺたっ!
こちらは形遊びをしながら実際に手を動かすことで、「自分で答えを導く力」や「自分で考えようとする力」が身につく玩具本です。本はマグネットになっているので、一度使ったら終わりではなく何度でも遊べるのも嬉しいポイントです。色や形を覚えるのにも最適です。
発売日:2020年11月
著者/編集:しみず だいすけ(著)
出版社:ポプラ社
ページ数:12p
◆ふみきりカンカン!のりものえほん
とくに乗り物が好きなお子様におすすめの一冊!ハンドルやマスコン(電車の操縦かん)がついていて、運転あそびができるだけでなく、いろんな働く車のリアルサウンドが収録されているので、見て、聞いて、触って遊べる玩具本となっています。
発売日:2023年11月
著者/編集:−
出版社:コスミック出版
ページ数:−
◆ぶくぶく おふろ ぬれると色が変わる!
こちら題名のとおり、ぬれると色が変わる絵本なので、お風呂のお供にぴったりの1冊となっています。はっきりした発色、わかりやすい線のイラストがたくさんで、大人も子どもも夢中に。「何色になるかな?」「この生き物はなぁに?」というやり取りも楽しい!水遊びにもつかえますよ。
発売日:2018年12月
著者/編集:ハルトムート・ビーバー(絵) 鈴木 ユリイカ(訳)
出版社:世界文化社
ページ数:8p
◆シナぷしゅ
テレビ番組でおなじみ「シナぷしゅ」のマグネットシール絵本。使用されているマグネットは柔らかいので小さい子どもでも遊びやすく、繰り返し安全に遊べます。生活シーンに合わせたいろんな色、形のマグネットは本だけでなくいろんなところでペタペタ貼って楽しめます。
発売日:2021年12月
著者/編集:テレビ東京(監修)
出版社:小学館
ページ数:10p
◆音と光のでる絵本 スイッチくるくる
「くるくる回す」をテーマに、音と光を組み合わせた仕掛けがいっぱい!「くるくるギア」を回すとメロディーが流れ光り、「くるくるまど」を回すと窓から顔が現れて声が聞こえます。「くるくるつまみ」で音を変えられるほか、イラスト合わせの「くるくるスロット」や「くるくるビーズ」など、多彩な仕掛けで遊べます。
発売日:2022年11月
著者/編集:かしわら あきお(絵) みっとめるへん社(編)
出版社:成海堂出版
ページ数:6p
【知育本】どんな本を選べばいい?選ぶ際のポイント・選び方

たくさんの良い効果が期待できる知育本ですが、数多くの中から最適なものを選ぶのは大変ですよね。ここでは、知育本を選ぶ際のポイントや、年齢別の選び方のコツなどをまとめましたので、ぜひ参考になさってくださいね!
「その子」に合った知育本を選ぶポイント!
知育本を選ぶ場合は、子どもの成長段階や興味に合わせて本を選ぶことが大切になってきます。以下は知育本を選ぶ時に押さえておきたい選び方のポイントです。
- 安全性とデザインを重視する:特に低年齢向けの絵本は、安全性の高い素材で作られていることにも注目です。角が丸いデザインや誤飲しない工夫がされた本を選びましょう。
- 子どもの身近なテーマを選ぶ:動物や乗り物、食べ物など、子どもの日常に近いテーマの本を選ぶと、興味を持ちやすくなりますよ。
- 仕掛けや触覚の楽しさに注目:めくる、押す、引くといった仕掛けがある絵本は、遊びながら学べるため特に人気があります。
これらのポイントを押さえながら、ぜひお子さんと一緒にお気に入りの一冊を選んでみてくださいね!
年齢別!おすすめ知育本の選び方
知育本は、子どもの年齢に合ったものを選ぶことで、より大きな効果が期待できます。ここでは、知育本の選び方を年齢別にご紹介します。
2–3歳にぴったりの知育本
- 五感を活かして学べる本
この時期の子どもは、色や触覚を通じて学ぶのが大好き!
鮮やかなイラストや、触ったり動かしたりできる仕掛けがある本を選んでみましょう。
- シンプルで繰り返しのある物語
単純で繰り返しが多いストーリーは、理解しやすく記憶に残りやすいという特徴があります。
親子で一緒にページをめくりながら、新しい言葉や考え方を自然に学んでいけます。
4–6歳向けのステップアップ知育本
- ストーリー性のある本
感情や社会性が育つこの時期には、物語を通して他者の気持ちを考える力を育む本が最適。
- 学習要素のある内容
ひらがなや数字に興味を持ち始める子には、学びの要素が入った本を選ぶのも良いでしょう。
親子で内容を確認しながら、新しい知識や考え方について会話しながら楽しめると良いですね。
まとめ
知育本は、遊びを通じて楽しく学べるだけでなく、親子の絆を深めるのにもぴったりです。
最近は、ただお話を読むだけじゃなく、遊びながら自然と学べる工夫がいっぱい詰まった「知育本」がたくさん出版されています。色鮮やかな絵、触ってみたくなる仕掛け、そして、わくわくする物語。
お子さんの興味や年齢に合った知育本を選び、それを日常に取り入れ、一緒に楽しい時間を過ごしてみてはいかがでしょうか?
(執筆者:yuffy)
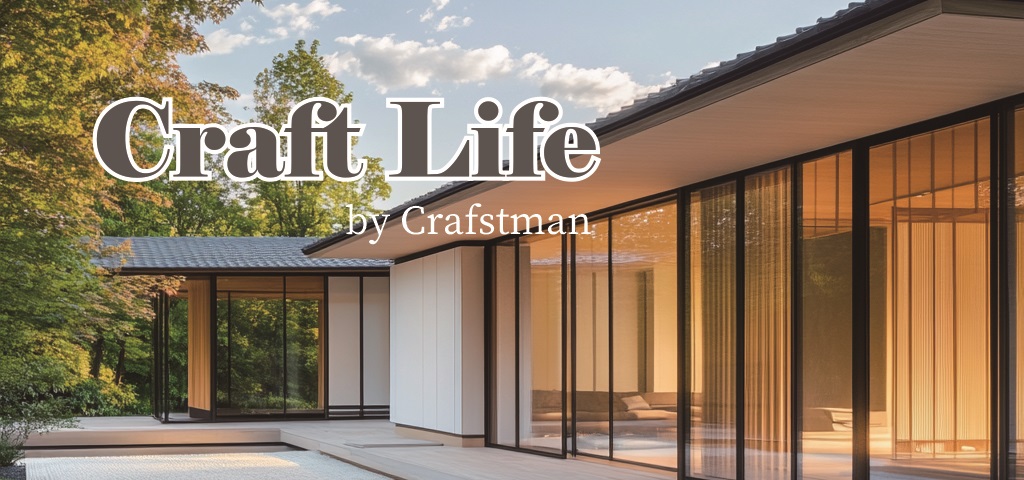

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4414811e.6c9303e0.4414811f.22f8515a/?me_id=1213310&item_id=13170094&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1113%2F9784052031113_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4414811e.6c9303e0.4414811f.22f8515a/?me_id=1213310&item_id=10646357&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0103%2F9784033280103_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4414811e.6c9303e0.4414811f.22f8515a/?me_id=1213310&item_id=20777978&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3772%2F9784023333772_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4414811e.6c9303e0.4414811f.22f8515a/?me_id=1213310&item_id=13272813&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4810%2F9784893094810_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4414811e.6c9303e0.4414811f.22f8515a/?me_id=1213310&item_id=10170844&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2188%2F9784834002188.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4414811e.6c9303e0.4414811f.22f8515a/?me_id=1213310&item_id=20163974&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8240%2F9784591168240.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4414811e.6c9303e0.4414811f.22f8515a/?me_id=1213310&item_id=21109151&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8802%2F9784774738802_1_4.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4414811e.6c9303e0.4414811f.22f8515a/?me_id=1213310&item_id=19381969&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8314%2F9784418188314.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4414811e.6c9303e0.4414811f.22f8515a/?me_id=1213310&item_id=20506132&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5050%2F9784099425050_1_15.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4414811e.6c9303e0.4414811f.22f8515a/?me_id=1213310&item_id=20807667&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1942%2F9784415331942.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

