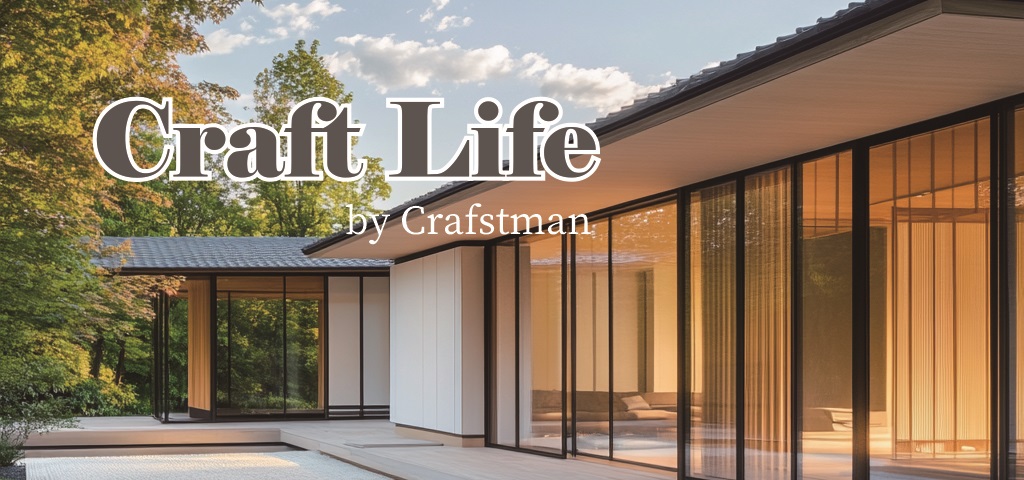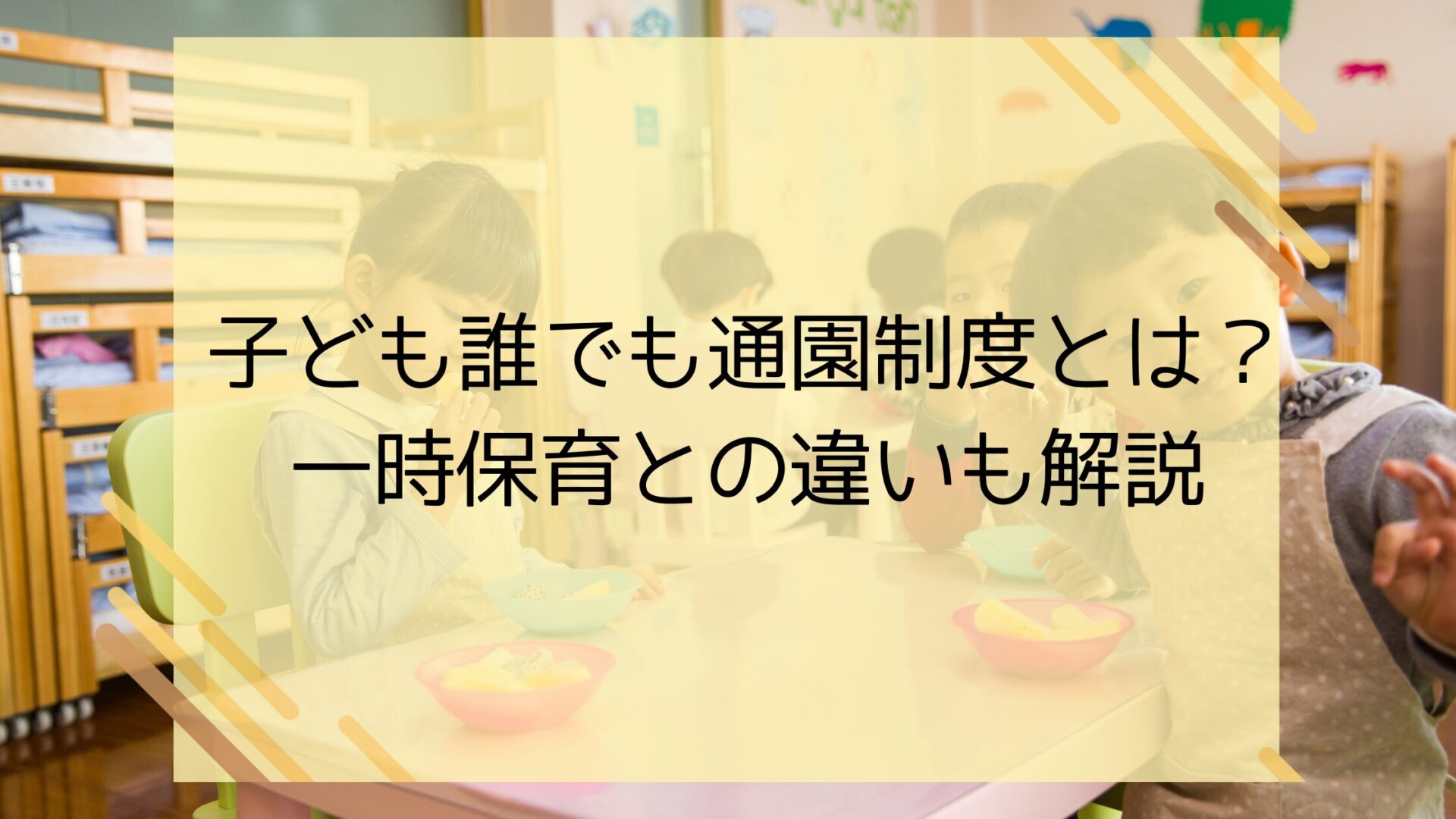(更新日:2025年4月11日)
乳幼児期の育児は、孤独を抱えやすいと言われています。
筆者も現在、生後8か月の娘を育てていますが、夜泣きの時期で日々ヘトヘトです。気晴らしに出かけようにも授乳があるため予定通りに進まず、まだ歩けないため遊びのバリエーションも限られており、結果として家にこもりがちな毎日となってしまっています。
そんな保護者を支援するために、2026年度から「子ども誰でも通園制度」が全国的に実施されることになりました。筆者の自治体では2025年からスタートしたようで、利用しようと計画しているところです。今回は、「子ども誰でも通園制度」の内容やメリット、モデル事業の利用者の声を紹介します。
子ども誰でも通園制度とは?

子ども誰でも通園制度は、保護者の就労状況に関係なく、 0~2歳を含む未就学の子どもが保育所や幼稚園などに通えるようにする新しい制度です。
この制度は、2023年6月に発表された「こども未来戦略方針」の一環として創設され、2026年度から本格的に実施されます。子ども1人あたり月10時間まで利用可能です。ただし、2026年度からは「月10時間以上で内閣府令で定める時間」とすることが発表されており、将来的には利用可能時間が増える可能性があります。
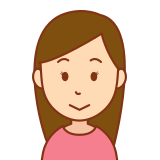
今までは、就労、病気や介護など事情がある人しか預けづらかったけど、「誰でも」月10時間までは預かってもらえるってことなのね!
子ども誰でも通園制度がスタートした背景と目的
子ども誰でも通園制度がスタートした背景と目的は以下の通りです。
背景
- 0〜2歳児の約6割が就園していない状況。
- 在宅で子育てをする世帯の子どもたちが、同世代の子どもと関わる機会が限られていること。
- 多くの保護者が「孤立した育児」の中で不安や悩みを抱えていること。
目的
- すべての子どもの育ちを応援し、良質な成育環境を整備すること。
- 多様な働き方やライフスタイルに関わらず、全ての子育て家庭に対して支援を強化すること。
- 子どもに対して、家庭とは異なる経験や、家族以外の人と関わる機会を提供すること。
- 保護者の子育ての負担軽減や孤独感の解消を図ること。
- 少子化に対応し、保育所等の在り方を見直すこと。
親の就労状況に関わらず、0〜2歳の子どもが保育施設を利用できるようにすることで、子どもの発達支援と保護者支援の両面から、日本の子育て環境の改善を目指しています。
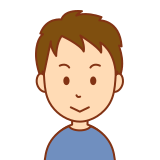
妻が専業主婦なんだけれど、育児にストレスを抱えているようだから、利用をすすめて見ようかな!…でも、一時保育と何が違うの?
一時保育との違いは?
よく、子ども誰でも通園制度は、従来の一時保育と何が違うの?と話題に上がります。違いを表にまとめました。
| 目的 | 利用条件 | 利用時間 | 対象年齢 | 実施場所 | |
| 一時保育 | 保護者の緊急時や一時的な保育ニーズへの対応 | 保護者の就労や病気、育児リフレッシュ | 数時間から数日間の一時的な利用、上限は市町村で異なる | 対象は0歳から就学前だが、施設によってその幅は異なる | 認可保育所、認証保育所、認定子ども園 |
| 子ども誰でも通園制度 | すべての子どもの生育環境向上と、多様な家庭のニーズへの対応 | 保護者の就労状況等に関係なく利用可能 | 2024年の試行的事業では、月10時間を上限としている | 生後6か月~2歳を含む未就学児全般 | 保育所や幼稚園 |
子ども誰でも通園制度は、より包括的で長期的な子育て支援を目指す制度であるのに対し、一時保育は保護者の就労や病気など、短期的で緊急時のニーズに対応するサービスという違いがあります。
料金の違いは?
子ども誰でも通園制度の利用料金は、自治体や施設によって異なるものの、多くの場合1時間300円が標準とされています。
一方一時保育は、1時間400円~800円、1日2000円~3000円程度となっています。
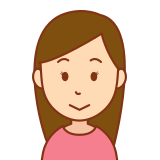
子ども誰でも通園制度のほうが、経済的負担も軽く済むのね。利用目的や頻度に応じで、上手に利用していきたいわ。
子ども誰でも通園制度 利用の流れ
では、実際に利用する際はどのような流れになるかを解説します。
子ども誰でも通園制度が実施されている園を確認
子ども誰でも通園制度が実施されている園は限られています。お住いの自治体のホームページから実施園を確認し、自宅からの距離などから利用しやすそうな園をピックアップしましょう。
利用のための手続き
子ども誰でも通園制度を利用するには手続きと事前の面談が必要です。手続きの流れは以下の通りです。
- 利用登録
- 利用登録専用フォームにアクセスし、子どもと保護者の情報を登録します。
- 登録は利用希望日の2週間前までに行う必要があります。
- インターネット申請が難しい場合はコールセンターに連絡します。
- 利用登録結果の通知
- 市による審査(3〜5日程度)後、メールで結果が通知されます。
- 事前面談の予約
- 登録完了通知を受け取った後、利用希望施設に直接連絡して面談を予約します。
- 予約は面談希望日の1週間前までに行います。
- 事前面談の実施
- 子どもの様子の確認や必要な物の説明などが行われます。
- 時間は約10〜30分程度です。
- 利用開始
- 面談後、施設の利用が可能となります。
利用したい時にすぐできるように、利用したい方は前もって登録しておくのが良さそうですね。
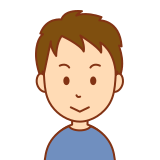
登録が済んでしまえば、あとは利用したい日に予約を取ればいいのか。
親たちのリフレッシュに使うのもイイかもな。
利用当日の流れ
利用当日の流れは以下の通りです。
- 登園
予約票と利用に必要な持ち物(着替えやおむつなど)、利用料を持ち、子どもと登園します。 - お迎え
約束した時間にお迎えに行きます。必要に応じて、次回の予約を相談することができます。
子ども誰でも制度を利用するメリットとデメリット
メリットは以下の3つです。
- 育児負担の軽減
- 子どもの発育促進
- 専門家のサポート
家で子どもと二人きりで過ごすことが続くと、保護者にとって体力的、精神的な負担が大きくなりがちです。産後うつのリスクも高まります。そんな時に、短時間でも子どもを預けてリフレッシュすることができれば、保護者のストレスや孤立感を軽減する助けになります。
また、同年代の子どもと関わることによって、子ども自身が刺激を受け、発達が促進されたり、社会性が養われたりするというメリットもあります。さらに、専門家に育児の相談ができることから、保護者はより安心して育児に取り組むことができるようになるでしょう。
デメリットは以下の4つです。
- 保育現場の負担増加
- 安全面の懸念
- 子どもへの影響
- 財政面の課題
最も大きなデメリットとして挙げられるのは、保育現場の負担増加です。現在、保育士不足が深刻な問題となっている中で、個々の子どもの特性を把握したり愛着を形成したりする前に、乳幼児を細切れで次々と受け入れることになるため、保育士の負担は一層増加するでしょう。また、環境に慣れていない子どもを預かる場合、事故を防ぐための特別な配慮や労力が通常以上に求められるため、安全面にも懸念が生じます。
子ども誰でも通園制度 モデル事業の利用者の声
子ども誰でも通園制度は2026年度の全国展開を目指し2023年度から実施され、2024年度には約150の自治体で試行的な事業が行われています。利用者からは以下のようなポジティブな声がよく聞かれています。
- リフレッシュ効果: 多くの保護者が「自分の時間ができた」「リフレッシュできた」といった感想を寄せています。子どもを預けることで、育児に対する心の余裕が生まれたと感じる親が多いようです。
- 子どもの成長: 子どもが保育園での給食や友達との関わりを楽しむ様子が見られ、「他の人との関わりができて嬉しい」といった意見があります。また、発語やコミュニケーション能力の向上を実感する親も多いです。
- 親子関係の改善: 「子どもと離れる時間ができたことで、よりかわいく感じられるようになった」という声もあり、親子関係が良好になったと感じる親が多いようです。

特に事情が無くても預けられるようになったことで、孤独を抱えがちな0~2歳の育児中の親にとって大きな味方となっているようです。
保育士からの反応

子ども誰でも通園制度に対し、現場の保育士の反応は様々で、以下のような声が上がっています。
ポジティブな反応
- 制度の有用性: 「保護者の負担軽減」や「孤立した育児を支える場になる」といった意見が多く寄せられています。また、地域の少子化に対する対策としても期待されています。
- 子どもの社会性の向上: 「子どもが集団生活を通じて社会性を身につける機会が増える」といった前向きな意見もあります。
ネガティブな反応
- 負担増加の懸念: 「毎日異なる子どもを預かることで個別対応が難しくなる」という不安があります。また、9割の保育士が制度開始に対する不安を抱いており、その理由として「保育士確保」や「安全面の管理」が挙げられています。
- 実施への不安: 「毎日異なる子どもが来ることで、既存の園児への影響や情緒不安定を引き起こす可能性がある」といった懸念もあがっています。また、書類や事務作業の増加による保育士の負担増加も心配されています。
ポジティブな声も上がる一方で、負担が増える心配や既存の園児への影響を心配する保育士も多いです。現場に丸投げするのではなく、適切な人員配置や待遇改善、業務の負担軽減などが政府に求められています。
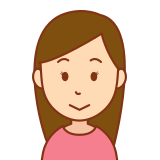
気持ちよく利用させてもらうために、保育士さんの待遇改善も同時に行ってほしいわね。
【まとめ】子ども誰でも通園制度 今後の展望
すでにモデル事業として実施されているなかで、子ども誰でも通園制度は利用者からポジティブな声が多数寄せられています。
孤独を抱えやすい乳幼児の育児をする保護者にとって、大きな味方になってくれそうな制度と言えるでしょう。
また、子どもを預けるだけでなく、保護者同士の交流促進や子育てに関する保育士からの情報提供、相談支援なども期待されています。ますます少子化が進んでいる昨今ですが、より子育てしやすい社会に向けての大きな支援策の一つといえます。
一方で、現場の保育士の負担増加への懸念は大きいです。2026年の本格制度化に向けて、保育の現場からのフィードバックを基にした改善策が求められています。
(執筆者:AKKA)