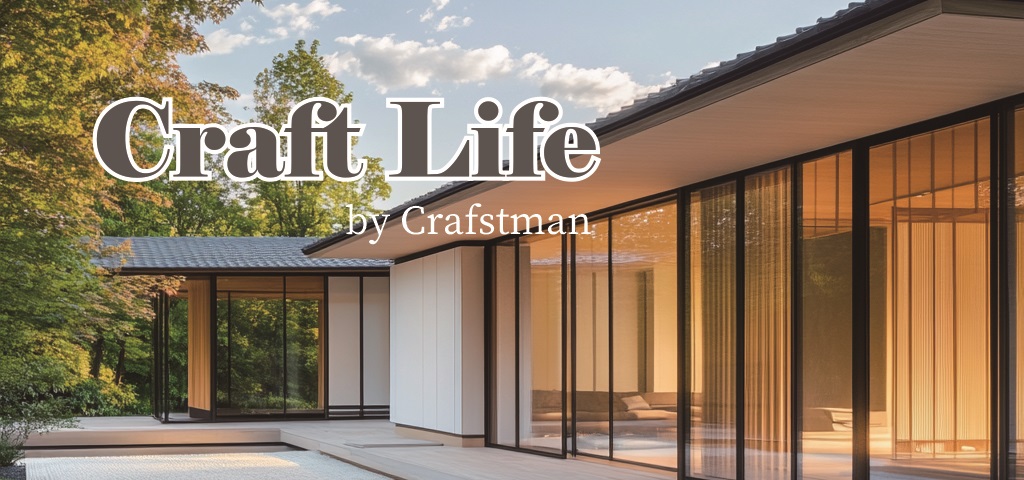(更新日:2025年4月5日)
共働き家庭は2000年ごろには5割を超え、2024年の調査では7割近い世帯が共働きであるという調査結果があります。
今では共働き家庭のほうが主流になっていると言えるのに、時代が変化しても共働き家庭の大変さは解消されていないように感じます。特に「小1の壁」は誰しもが頭を悩ませる問題で、仕事を続けられるのかと不安になることもあるでしょう。
わたしは小学生の子どもが2人いますが、それぞれが小学生になったときに「保育園時代より大変かも」と感じました。
今日は小学生の子どもを抱えてどのように共働きを成功させるか考えたいと思います。
就労する親の味方である学童、しかし思わぬ落とし穴も
子どもが小学生になるときに、まず預け先の候補になるのが公営の学童ではないでしょうか。
保育園に代わって週5日学童に行くものと親は考えると思います。
しかし昨今、希望して学童に入れないという事態が発生しています。
数年前は保育園の待機児童が話題でしたが、そのころの問題が小学生になって再び浮上している状態ですね。
運よく学童に入れた場合も、子どもが行き渋ったという話もよく聞きます。
保育園と比べて一つの空間にいる子どもが多くガヤガヤした雰囲気に馴染めなかったり、おもちゃが少なくて飽きてしまったり、クラスで仲が良くなった子が学童に行かない子だったり。
なかなか保育園のように、「第二の家」にいるような気持ちで過ごせず、行きたくないという気持ちが芽生えることがあるようです。
学童の先生に相談することで解消できる問題もありますが、根本的は改善に至らないケースもあり、その場合は他の選択肢にも目を向けてもいいかもしれません。
▼参考記事(2024年12月24日)▼
学童登録児童過去最多!こども家庭庁・文科省は待機児童対策も踏まえ「放課後児童対策パッケージ2025」発表
公営以外の学童、「民間学童」という選択も
民間学童の存在は聞いたことがあるでしょうか。
民間学童とはNPO法人や株式会社が自治体を通さずに運営する施設です。
公営と比べて価格が高い一方、独自のカリキュラムがあったり預かり時間が長かったりなど、公営にないメリットがたくさんあります。
特に学童施設内にいる時間で習い事近いプログラムを受けられるサービスは人気で、値段は高くてもそのサービスを受けたいということで民間学童に行かしている人が多いです。
民間学童は週1,2日でも利用できるところがあり、公営と民間どちらも契約して、曜日で分けて利用している人もいます。
長期休みだけ利用できるプログラムを用意しているところが多いので、まずは短期利用で様子を見てもいいかもしれません。
放課後に「習いごと」に行かせる

保育園時代、平日は仕事があるから習い事は土日にしているという家庭は多いのではないでしょうか。
平日に送迎しなくていい一方、土日が習い事で時間がつぶれてしまうデメリットがあります。小学生になったら思い切って平日に習い事に行かせてみてもいいでしょう。
子ども1人で歩かせるのが不安なうちは、シッターや地域のファミサポさんに送迎をお願いするのも手です。わたしの友人はファミサポさんに学童にお迎えに行ってもらいそのまま習い事の送迎へ、その後習い事のお迎えはどちらかの親が行くというスケジュールを組んでいました。
もし1人で行かせるのであれば、いくつかの点に注意しながら習い事までの道のりを何度か子どもと練習しましょう。
わたしが自分の子どもが習い事に行くときに注意していることは以下の点です。
1.できるだけ明るい時間に往復できるレッスンを選ぶ
夕方になるほど交通量は多くなり、事故につながりやすい傾向にあります。また、放課後から習い事に行くまでの時間を長くしないためにも、習い事時間が前倒し可能か確認してみましょう。
2.キッズ携帯を持たせる
やはり連絡が取れたほう便利です。GPS機能付きのものが多くさらに安心。
3.自転車は使わない
自転車だとどうしてもスピードが出てしまったり、交通ルールをまだきちんと把握していない場合があったりします。よりリスクを減らすため歩きや公共交通機関を利用させています。
番外編
周りから聞いた話でおもしろいと思ったケースを紹介します。
1.そろばん教室に行く
近所に定額通い放題のそろばん教室があり、学童代わりに毎日そこに行かせているとのこと。宿題もみてくれるそう。
個人でやっている教室なので先生が趣味の範囲で対応しているめずらしいケースです。
2.学童に中抜けの制度があり、何人かでまとまって公文に行く
学童の中抜け自体は認めているところもあるそうなのですが、友人の子が通う学童は「公文に通う子たちがみんなで中抜けし、公文に行く」という文化があるそうです。
こちらもレアでラッキーなケースだとは思いますが、特に低学年の場合1人で中抜けさせるのは不安でも複数人いるとなるとなんとなく安心ですね。
まとめ
小学生になると子どもが自分でできることが増え、保育園の送迎もなくなり子育てがかなり楽になると思っていました。
ところが、保育園時代にはなかった、学校の長期休みや行事の振替休日、さらには学級閉鎖とさまざまな問題が立ちはだかります。
会社では子どもが小学生になるころに時短勤務制度が終了することもあるでしょう。
どうしよう?と八方ふさがりに感じることもあるかもしれませんが、子どもも成長しています。
学童や習い事をはじめ、その子にベストな放課後の過ごし方を見つけて、小学生時代の共働きを一緒に乗り越えましょう。
(執筆者:ぴすこ)